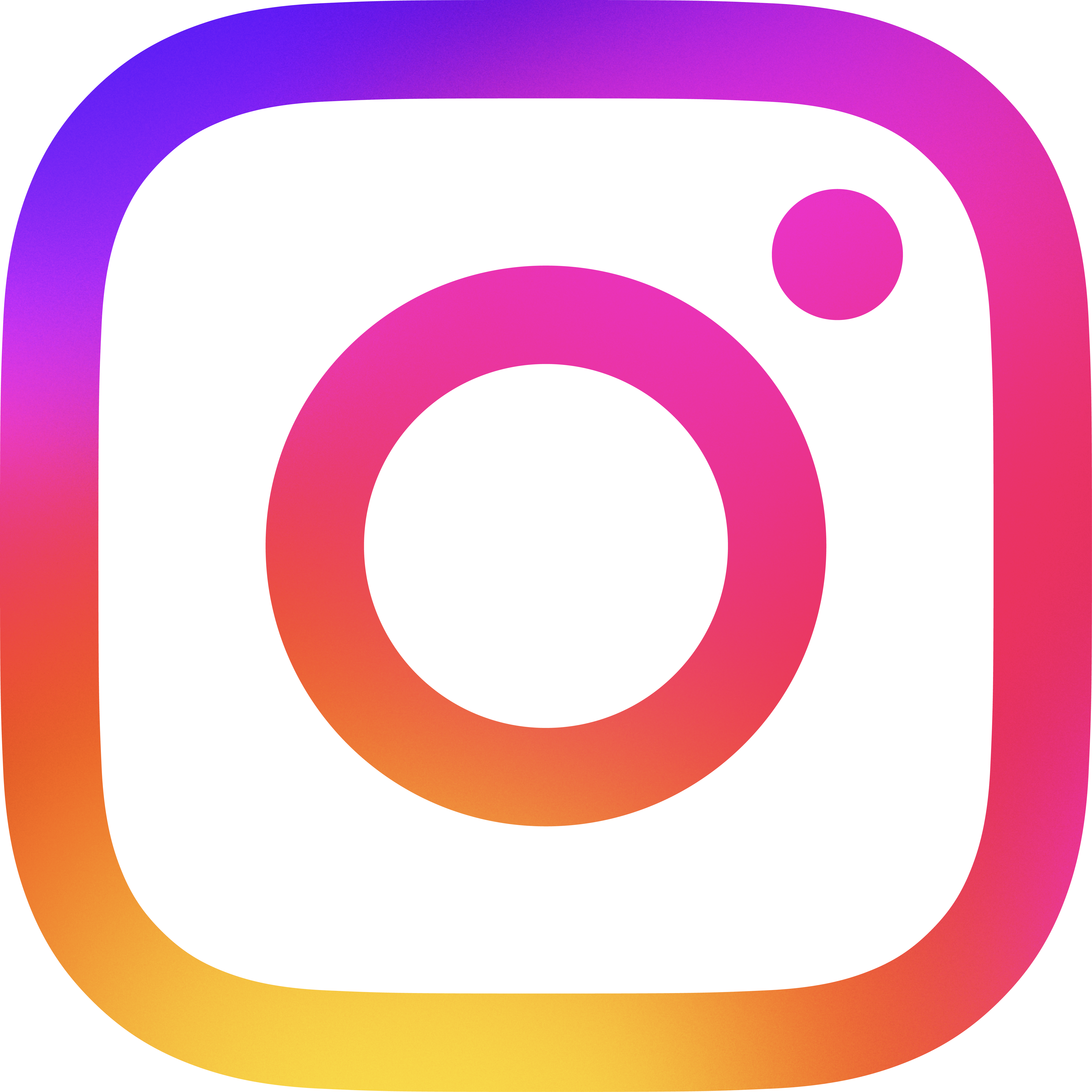運行管理者の資格は国家資格なので試験が必須と思われがちですが、5回の一般講習や5年の実務経験があれば、試験を受けずに取得可能です。
こちらでは、試験を受けずに運行管理者の資格を取る条件や方法を紹介するので参考にしてください。
この記事のまとめ
・運行管理者は試験なしでも取得可能
・試験なしでの取得条件は5年の実務経験と5回の講習
・講習は1年に複数回受けても1回とみなされるので要注意
運行管理者の資格は国家試験を受けなくても取れる

まず、そもそも運行管理者とはどのような資格で、どのような仕事をするのか、また資格の取得条件はどうなっているのかを解説します。
運行管理者とは
運行管理者とは、バスやトラックなどの事業者用車両を運転するドライバーの管理や配車手配、運行ルートなどを指示する人およびその資格を言います。
ドライバーが日々安全運転をおこなえるような指導と、法令に則った勤務管理をおこなう運送業において重要な立場です。
運行管理者になるための条件
運行管理者は国家資格であるため、まずは資格を取得しなければいけません。この資格の取得方法は2つあります。
資格試験に合格する
最も一般的な方法は資格試験に合格することです。
試験は年に2回(通常3月と9月)開催されています。受験資格は2つあり、1つ目は運行管理者の補助業務を1年以上経験していることです。
もう一つの受験資格は、事前に3日間の基礎講習を受講していることです。
基礎講習は資格試験の出題範囲を授業で習うため、実務経験がある方でも試験前に受講することが推奨されています。
運行管理者に選任された後、基礎講習がまだの方は受講しなければいけません。
どちらにしても受講しなければいけないので、試験前に受けておくといいでしょう。
所定の条件をクリアする
もう1つの条件はある条件をクリアすることです。その条件とは、「5年の実務経験と5回講習に参加すること」です。
この場合だと資格試験を受験しなくとも資格が与えられ、試験勉強の手間や受験費用の節約にもなります。
実は資格試験の合格率は30%台と難易度が高く、簡単には合格できない内容となっています。
そのため、試験を受けずとも資格が取得できるこの方法も意外と人気があるのです。
こちらの方法について、次の章でもう少し踏み込んだ解説をしましょう。
参考:貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条|e-GOV 法令検索
関連記事:運行管理者資格の試験難易度を解説!資格取得の近道とは?
関連記事:【2022最新】運行管理者の資格試験におすすめのテキスト!勉強方法もあわせて紹介します。
運行管理者の取得に必要な5年の実務経験
実務経験として認められる仕事内容は、運行管理に関する仕事の補助業務です。
要するに、運行管理者の補助者として5年間実務経験をおこなえば、1つ目の条件がクリアされることになります。
この補助業務がどういった仕事かは以下のようなものになります。
- 点呼の一部分
- 運行指示に関する資料作成やドライバーへの伝達業務
この点呼の一部分とは、点呼の1部を行うのではなく、点呼できる回数が制限されているということです。
点呼は毎日出勤時と退勤前に行うことが義務付けられています。
その点呼をおこなう中で、1か月間の全点呼回数の3分の2までは、補助者がおこなってもいいとされているのです。
たとえば、点呼を1日に2回行う事業者で1か月が30日だった場合、この月の全点呼回数は60回になります。
つまり、補助者はその3分の2である40回まで点呼を代わりに実施できるのです。
もう一つの資料作成やドライバーへの伝達業務に関してですが、まず補助者自身の資料を作ることはできません。
あくまで運行管理者が考えた内容を補助者がまとめるというものになります。
運行管理者の指導・監督のもと業務をおこなっていると考えましょう。
伝達業務も同じです。例えばドライバーの体調が優れておらず、運行に支障が出そうだなと感じた場合、運行管理者にその旨を伝えて、運行できるかどうかの指示をもらいます。
そのあと、もらった内容の指示をドライバーに伝えるのが仕事です。
他にもアルコールが確認できた場合や速度違反を行った場合など、ドライバーの過失による問題などが発覚すれば、直ちに運行管理者に報告するのも補助者の仕事になります。
運行管理者の取得に必要な5回の一般講習
この条件に当てはまる講習とは、運行管理補助者として勤務している間に受講したものとされています。
この講習は基礎講習と一般講習の2種類あり、5回のうち、1回は基礎講習を受講しなければいけません。
ここで注意しなければいけない点として、講習の順番があげられます。
まず一番初めに基礎講習を受講することが必須となっています。
というのも基礎講習を受講することで補助者として選任されるからです。そのため、一般講習を受講する前に基礎講習を先に済ませておきましょう。
また、講習は1年に1回までしかカウントされない仕組みとなっています。
まとめて一気に講習をうけても1回としかカウントされないので注意しましょう。
この1年とは4月から翌年3月の期間になります。最初に基礎講習を受講し、そのあと1年に1回ずつ一般講習を受講して条件を満たすようにしましょう。
なお、運行管理者を募集する求人の中には、資格取得を支援してくれる会社もあります。
求人情報は以下のボタンをクリックしてチェックしてください。
一般講習のカウント方法が平成19年に変更された点に注意
5年の実務経験や5回の一般講習への参加によって、運行管理者の資格を取得できることは既に述べた通りです。
しかし、注意したいのは平成19年に起きたルール変更によって、一般講習のカウント方法が変更された点です。
そこでこちらでは、ルール変更やカウント方法、カウントの事例について詳しく解説します。
1年に5回受講してもカウントは1回
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第24条には、「基礎講習又は一般講習を同一年度に受講した場合1回とする」と明記されています。
これはつまり、同一年度に何回一般講習を受講したとしても、1回としてカウントされることを意味します。
早く運行管理者の資格が欲しいからと言って、1年の間に5回連続で講習を受講しても、資格の取得条件を満たせません。
1年に何度講習を受けても1回としかカウントされないので、条件を満たすためには毎年1回ずつ受講する必要があり、最低5年はかかります。
平成19年にルール変更があった
平成19年度に運行管理者の「補助者制度」が始まりました。それまで運行管理者の代わりを務めていた「代務者」から「補助者」へ変更されたのです。
ただ、ここで変わったのは名称だけではありません。
制度の開始に伴って、運行管理者資格の取得に必要な講習のカウント方法が以下のように変わりました。
【旧】
受講回数5回のうち、何番目でもいいので1回基礎講習を受講しなければならない。
【新】
平成19年4月1日以降に基礎講習を受けたなら、それ以前に受講していた一般講習はノーカウント。ただし、代務者経験時に受講した一般講習はカウントされる。
講習のカウントの事例
講習はカウント方法が複雑ですので、事例を2つ紹介します。z
制度変更前に代務者経験があった人の場合
| 年度 | 受講内容 | カウント |
| 平成16年度 | 一般講習を受講 | ○ |
| 平成17年度 | 一般講習を受講 | ○ |
| 平成19年度 | 運行管理者補助者制度が開始 | - |
| 平成20年度 | 基礎講習を受講 | ○ |
| 平成23年度 | 一般講習を受講 | ○ |
| 平成25年度 | 一般講習を受講 | ○ |
この方の場合は代務者経験があるので、平成19年度より前に受講した2回分の一般講習はカウントされます。
つまり、平成25年度の受講によって、回数に関しては取得要件を満たしている事例です。
ちなみにこの方の場合、代務者時代の期間が実務年数に加算されるため、「5年の実務経験」という要件も満たしています。
代務者経験がない人の場合
| 年度 | 受講内容 | カウント |
| 平成21年度 | 一般講習を受講 | ×-① |
| 平成22年度 | 基礎講習を受講 | ○ |
| 平成22年度 | 一般講習を受講 | ×-② |
| 平成25年度 | 一般講習を受講 | ○ |
| 平成26年度 | 一般講習を受講 | ○ |
この方の場合、新しいルールが適用されるので、基礎講習より前に受講した一般講習はカウントされません(①)。
また、平成22年度に基礎講習と一般講習を2つ受講していますが、1年に何回受講してもカウントは1回ですので、同年度の一般講習はノーカウントです(②)。
つまり、この方は5回の受講回数のうち3回しかカウントされていません。
あと2回受講する必要があるので、この方が取得要件を満たすには最低でもあと2年はかかります。
基礎講習・一般講習の内容や申し込み方法

運行管理者の資格を取得するために、基礎講習と一般講習の受講が必要と紹介しました。
それではこの基礎講習と一般講習の内容や申込み方法などについて解説していきましょう。
基礎講習
基礎講習は独立行政法人NASVAなどが開催しています。
この基礎講習を受講すると運行管理の補助者ができるようになります。
このほかに通常であれば、1年以上の実務経験が受験資格である運行管理者の資格試験を受けることができます。
講習時間や講習場所
講習は3日間かけて行われており、合計16時間の講習時間があります。
NASVAの場合、講習場所は全国各地にある支所です。
貨物の場合は年に4回、旅客の場合は年に2回程度開催されています。受講料は8,900円で開催日に現金にて支払います。
申込みはNASVAのホームページ、もしくは郵送によって可能です。
基礎講習は運行管理者に選任された後、過去に受講していないものは必ず受けなければいけません。
つまり、運行管理者になるものはどちらにしても必ず受講しなければいけない講習となっています。
参考:基礎講習|NASVA
基礎講習の内容
基礎講習では、3日間かけて道路交通法や道路運送車両法などといった法律に関することや運行管理の業務に関すること、事故防止に関することなど、業務上必要な知識をみっちり叩き込まれます。
最終日には修了試験もおこなわれるので、最後まで気が抜けません。
一般講習
一般講習も基礎講習と同じくNASVAが主催しています。
運行管理者の補助者として5年間働いている間に、4回受講すれば運行管理者の資格が与えられます。
また、運行管理者に選任された後も、2年に1回は必ず受講するのが義務です。
受講しなければ資格が剥奪される可能性があるので注意しましょう。
講習場所や講習時間
一般講習がおこなわれるのは、全国各地の支所で基礎講習がおこなれる会場と同じです。
講習は1日かけておこなわれます。1か月の間に複数回行われるため、自分の都合のいいときに受講することが可能です。
予約はNASVAのホームページ、または電話などで受け付けていますが、3日前までの申込みが必須となっています。
講習費用は3,200円で、当日受付時に支払うことになっています。
講習内容について
一般講習の内容は自動車運送業における法令や運行管理の業務に関すること、ドライバーの指導及び管理に関することなど、日常業務に関わる内容の復習や変更事項などが伝えられます。
講習修了時には修了証書が授与されます。失くさないように保管しておきましょう。
参考:基礎講習|NASVA
資格を取得した後の流れ
運行管理者の資格を取得したあとの流れについて紹介していきましょう。
資格試験に合格した人の場合
資格試験に合格した人は合格発表から3か月以内に所定の書類を準備して、所轄の運輸局に資格証の交付申請手続きをおこないましょう。
3か月を過ぎてしまうと合格が無効になります。絶対に忘れないようにしてください。
5年の実務経験と5回講習の参加経験がある人の場合
こちらの場合は資格を交付するにあたって運輸支局に資格証の交付申請をおこないます。
実務経験の証明書は会社に発行してもらいましょう。
「運輸管理に関する実務経験証明書」という書類にハンコを押してもらい、この書類を提出した後、資格が交付されます。
資格が届いた後
資格が届いた後は運行管理者として選任されたという届出を行わなければ正式には認められません。
貨物の場合は選任から1週間以内に、旅客の場合は15日以内に届け出をおこないましょう。
届け出先は国土交通大臣です。ただし手続きを行うのは運輸局の支局になります。
届出の際に必要なものは下記のとおりです。
- 運行管理者選任・解任届出書
- 運行管理者資格者証の写し
この選任・解任の届出書は国土交通省や運輸局のHPからダウンロードできます。
運行管理者の配置人数
運行管理者はバスやタクシーなど人を乗せて賃金をとる「旅客」と、トラックや軽バンなどに荷物を載せて運ぶことで賃金をとる「貨物」の2種類があります。
運行管理者は営業所に配置しなければいけませんが、人数は保有している車両の数によって異なります。
同じ車両数でも、旅客と貨物とで配置人数が異なるため、詳しく解説しましょう。
貨物
1~29台:1名
30~59台:2名
60~89台:3名}
以降30台増えるたびに1名追加
旅客
旅客のなかでも貸切バスと乗合バスで少し条件が異なります。
タクシー/乗合バス
1~39台:1名
40~79台:2名
80~119台:3名
以降40台増えるたびに1名追加
貸切バス
1~39台:2名
40~59台:3名
60~79台:4名
以降20台増えるたびに1名追加
運行管理者の注意点
運行管理者に選任されたあと、気をつけるべき点について紹介していきましょう。
運転手との兼任はできない
運行管理者は基本的にドライバーを担当することができません。
運行管理者は点呼だけでなく、運行中の状況確認や渋滞時などの対応策の検討・指示、その他電話対応など行わなければいけない仕事が多いです。
特に営業所によっては運行管理者が1人しかいない場合があります。
ドライバーの人員不足だからといって運転をしてしまうと点呼や運行業務ができなくなります。
もし営業所に2人以上運行管理者がいる場合や、運行管理者の補助者がいる場合は運転手を行える場合があります。
ですが、運行管理者はなるべく営業所にとどまる方が業務の支障が起きにくいでしょう。
2年に1回講習を受けないといけない
運行管理者の資格は一度取得すると一生ものです。ただし、選任時は年度内(4月~翌年3月)、そのあとは2年に1回の講習を受講しないといけません。
運行管理者が受講する講習は「基礎講習」と「一般講習」、「特別講習」の3種類あります。
この場合の講習は一般講習に当たります。以前は講習の受け忘れがないように通知が来たのですが、今は通知が送られないようになりました。
手帳に書き込む、カレンダーに記すなど自分なりの対策をしましょう。
もし受講を忘れてしまった場合には行政処分(自動車等停止処分)が下される可能性があります。
この行政処分を受けた場合、特別講習を受講しなければいけません。
この特別講習は重大事故や法令違反によって行政処分を受けた運行管理者が受講しなければいけないものです。2日間にかけて合計13時間の講習があります。
また、行政処分を受けてしまうと国土交通省のHPに掲載されてしまいます。
もし掲載されてしまうと顧客から信頼性を失ってしまい、損害が出てしまう可能性があるので注意しましょう。
まとめ
運行管理者の資格を取得する方法として、一般的なのは資格試験を受験することです。
その理由としては、資格取得に時間がかからないためです。
しかし、すぐに資格を取る必要がない人や資格を取るか決めていない人は、今回のような5年の経験と5回の講習参加という方法もおすすめです。
運行管理者の補助者として仕事を続けていき、取得したいと思ったタイミングで資格の手続きをおこなえばいいだけです。
資格試験の勉強の必要もないので、気楽に取得できる方法でしょう。
どちらの取り方の方がいいとかはないので、1つの方法として知っておいていただければ幸いです。
運行管理者の方へ
【完全無料】日本最大級の運行管理者専用転職サービス



などの悩みがある方は、転職すべきタイミングです。
今、日本の運行管理を担える人材の数は減少しており、転職市場では、現職よりも年収などの条件が良い会社から内定をとれる確率が上がっています!
今回紹介するサイトは、日本最大級の物流転職支援サイト「ドライバーキャリア」です。
全国の物流企業の運行管理車向け求人情報を豊富に扱っており、10代~60代、全年齢に対応しています。地域/職種/給与/エリア などの詳細検索から、様々な求人を検索することができます。
お住いの近くにある求人を無料で検索する事ができます。検索はこちらから。
運行管理者の求人を1分で無料検索転職においては、希望の仕事内容や給与をもらえず、転職に失敗している方も非常に多いのが実態です。それは、情報収集が不足している事が原因にあります。
より希望にあった条件の会社があるにも関わらず、時間がなかったりすると、あまり探さずに転職を決め、ミスマッチに繋がってしまいます。
検索サイトの特徴は、
①無料で1分で簡単検索できる
②高年収の会社が見つかる
③勤務時間/仕事内容などの条件改善
などのメリットがあります。また無料でキャリアアドバイザーが条件に合った求人を代わりに探してくれるので、時間が無い方にも非常にオススメです!