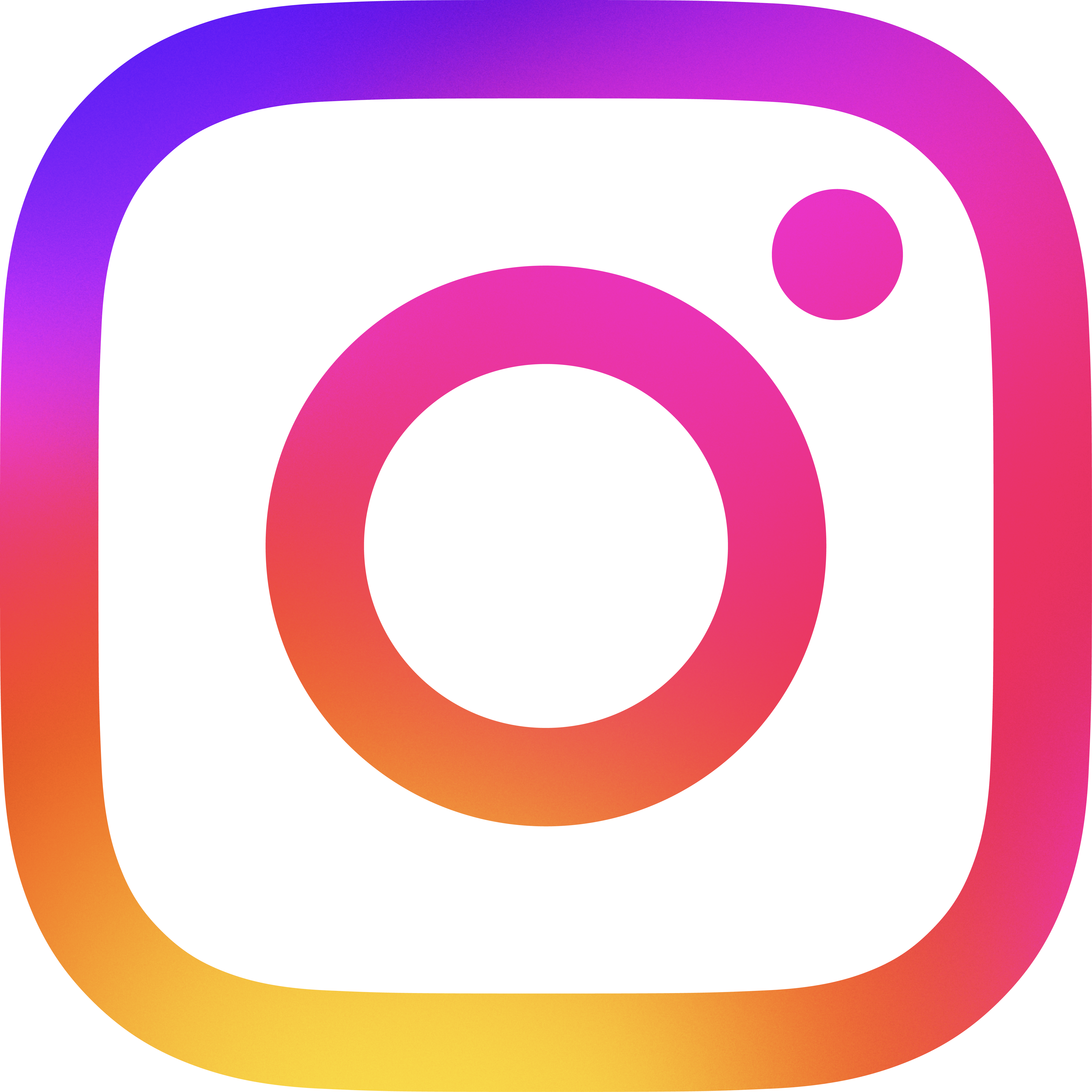バス運転手になるためには資格が必要です。
そこでこちらではバス運転手の仕事に就きたい人向けに、仕事内容や必要な資格の詳細を紹介する他、
費用の負担ゼロで資格を取得する方法も紹介します。
バス運転手への転職を検討している方はぜひ参考にしてください。
この記事のまとめ
・バス運転手になるには大型二種免許が必要
・資格支援制度を使えば費用ゼロで取得も可能
・バス運転手は将来性が高く安定した仕事
バス運転手に必要な資格・免許

どのような種類のバスを運転する場合であっても、バスの運転には資格や免許が必要になります。
バスを運転するために必要となる資格及び免許の種類は下の2種類です。
- 普通自動車免許(いわゆる普免)
- 大型自動車第二種運転免許
大型自動車第二種運転免許の資格は、略して「大型二種免許」ともいいます。
大型二種免許は以下の条件や基準に当てはまる大型車(バスなど)を運転するのに必要な免許であり資格です。
➀乗車定員30名以上
②総重量11t以上
③最大積載量6.5t以上
大型二種免許を取得するためには、まず普通自動車免許の取得が必要となります。
なぜなら、普通自動車免許を取得しないと、大型免許資格を得れないからです。
次に、二種免許に限らず大型免許資格を取得するためには、普通自動車免許取得から3年以上経過していることが条件になります。
よって、普通自動車免許を最年少の18歳で取得したとしたら、一種、二種にこだわらず大型免許を取得する資格を得るのは21歳のときです。
よく大型免許取得の年齢が21歳以上」と書かれているのはそのためです。
ちなみに大型二種免許の受験資格としては、普通自動車免許の他にも「大型一種免許・大型特殊免許のいずれかを取得して3年以上(自衛官は2年以上)」とあります。
大型特殊免許は大型一種免許と異なり、普通自動車免許を持っていなくても取得できる資格ですが、現実的に考えると普通免許から大型二種免許へと進むのがセオリーといえるでしょう。
大型二種免許の合格率
大型二種免許は受験自体のハードルは低い免許です。
しかし、大型二種免許の試験を初めて受ける場合の合格確率は例年10%未満とされ、決して簡単な試験ではありません。
運転するのに資格が必要なバスの仕事内容

バスはたくさんの人を一斉に目的地へ運ぶことに適した大型車ですが、用途に応じて路線バス・観光バス・高速バス・送迎バスの4つに分類されています。
こちらではそれらの特徴を順番に紹介します。
路線バス
一般的に最も馴染み深いバスが路線バスです。
路線バスは駅から各地域へ、または各地域間をを循環し、決まった時間かつ決まったルートで乗客を運びます。
また、移動距離が比較的短いのも特徴です。
主に街中を走るため、スピードを出すことはあまりありませんが、運転中は常に並走して走る自家用車等に注意する必要があります。
さらに、料金授受などで乗客とコミュニケーションを取るのも路線バスの運転手の仕事です。
なお、路線バスを運転するための資格としては、大型二種免許が必要になります。
観光バス
観光バスは、学生の修学旅行や社員旅行、そして旅行会社が企画したバスツアーといった団体での貸切りを対象にしており、主に観光目的で使用されるバスになります。
長距離移動が多くなるため、高速道路などでスピードを出して走行する場面も多いです。
また、路線バスと違って走行時間やルートも異なるケースが多いと言えます。
さらに、路線バスと比べて車体が大きいことも特徴的です。
運転には高度な技術が必要であり、長距離運転に耐えられるだけの集中力も必要となります。
必要な資格としては、路線バスと同じく大型二種免許が必要です。
高速バス
お手頃な価格で長距離を移動できる高速バスは、旅行などが好きな人にとってはコスパが最高にいい交通手段の1つです。
高速バスは高速道路などを使用して、都市間を結ぶ長距離移動をおこなうバスのことを指します。
朝から昼にかけて出発する高速バスのことを「昼行高速バス」と呼び、夜に出発し朝に目的地へ到着する高速バスのことを「夜間高速バス」とそれぞれ呼びます。
高速道路を主に走行するためスピードを上げて走る区間が多く、走行ルートは一定ですが、長距離移動の割には途中停車する場所がさほど多くありません。
バスの種類に関しては観光バスと同程度の大型バスを使用しますが、車種によっては車内が仕切り等でプライベート空間が確保されているため、観光バスほど多くの乗客を乗せることはできません。
観光バスと同じく運転技術のほかに長距離及び夜間走行も多いため、眠気に対する集中力が必要になります。
また長距離の割に停車数が少ないため、トイレに対する用心も心掛けなければなりません。
高速バスを運転するための資格としては、路線バス及び観光バスと同様大型二種免許が必要になります。
送迎バス
旅館及びホテルまたは幼稚園や保育園に通う園児たちの送り迎えなどに利用されるバスが送迎バスになります。
送迎バスに使用するバスとしては、路線バスよりもさらに小型のマイクロバスがよく使われますが、ミニバンやワンボックスカーが使用される場合もあります。
送迎バスを運転するための資格としては、普通自動車免許が必須ですが、大型二種免許に関しては必要なケースとそうでないケースがあります。
まず大型二種免許の資格が必要でないケースとしては、送迎先から直接依頼を受けて送迎をおこなう場合です。
一方、大型二種免許の資格が必要なケースは、送迎先から業務委託として仕事を請け負っている場合になります。
これは大型二種免許自体が、大型車を商業目的で運転する際に必要となる資格及び免許であることに起因しているのが理由です。
このように、同じバス運転手の仕事でもさまざまな仕事内容があります。
バス業界では運転手が不足している会社が多いので、免許のない未経験の方を採用するバス会社も珍しくありません。
未経験者向けのバス運転手の求人情報に興味がある方は、こちらのボタンをクリックしてください。
バス運転手になるにはどんな資格が必要?

バス運転手になるためには、普通自動車免許と大型二種免許の2つが必要です。
しかし、バス会社に入社するまでに必ず自分自身で大型二種免許まで取得しなければならないかというと、そうではありません。
バス会社に入社後でも、大型二種免許の取得が可能です。
そこでこちらでは大型二種免許資格に関して事前に免許を取得しておく場合と、入社後に取得する場合の両方のケースを紹介します。
事前に大型2種自動車運転免許を取得しておく
まず大型二種免許の受験資格として、普通自動車免許・大型一種免許・大型特殊免許のいずれかを取得して3年以上であることが必要です。
次に、大型二種免許資格を取得するための方法は以下の3つがあります。
➀運転免許試験場で直接受験する
②公安委員会指定の教習所を受講する
③合宿免許
➀のように運転免許試験場で直接受験する場合は、公安委員会指定の教習所を受講する場合と比べて費用は少なく済みますが、合格する確率は非常に低いです。
②と③の合格率は80〜90%であり、直接受験と比べて高いですが、その反面受講費用が約50〜60万円とかなり高額です。
ただし、普通二種免許及び大型一種免許を保有している場合は受講費用が約25万円位になります。
事前に大型二種免許を取得する場合は、どのケースであっても一長一短があるのが特徴といえます。
入社後に会社の支援を得て取得する
多くのバス会社では「大型二種免許取得制度」という資格支援制度を設けています。
実はこちらの制度を利用すれば、費用を自己負担して免許を取得する必要がありません。
資格支援制度の一環である大型二種免許取得制度は、バス会社における福利厚生の1つで、会社の支援によって大型二種免許取得を目指すものです。
支援の内容としては、「資格及び免許取得後数年間は勤務する」という条件付きながらも、教習中における費用について全額または一部を負担してもらえます。
また教習中のため、未資格の状態でも社会保険に加入できるといった支援を受けられるのです。
このような資格支援制度を設けているのは、自前の社員を育てたいという理由の他に、昨今の人手不足を解消したい狙いもあります。
また、きちんと働き方改革を実践している企業というイメージ戦略の1つとも言えるでしょう。
個人で大型二種免許の費用を支払うことが難しい場合は、バス会社の資格支援制度を活用するのも手です。
資格支援制度があるバス会社の求人情報を確認する場合は、以下のボタンをクリックしてください。
バス運転手の資格試験の難易度
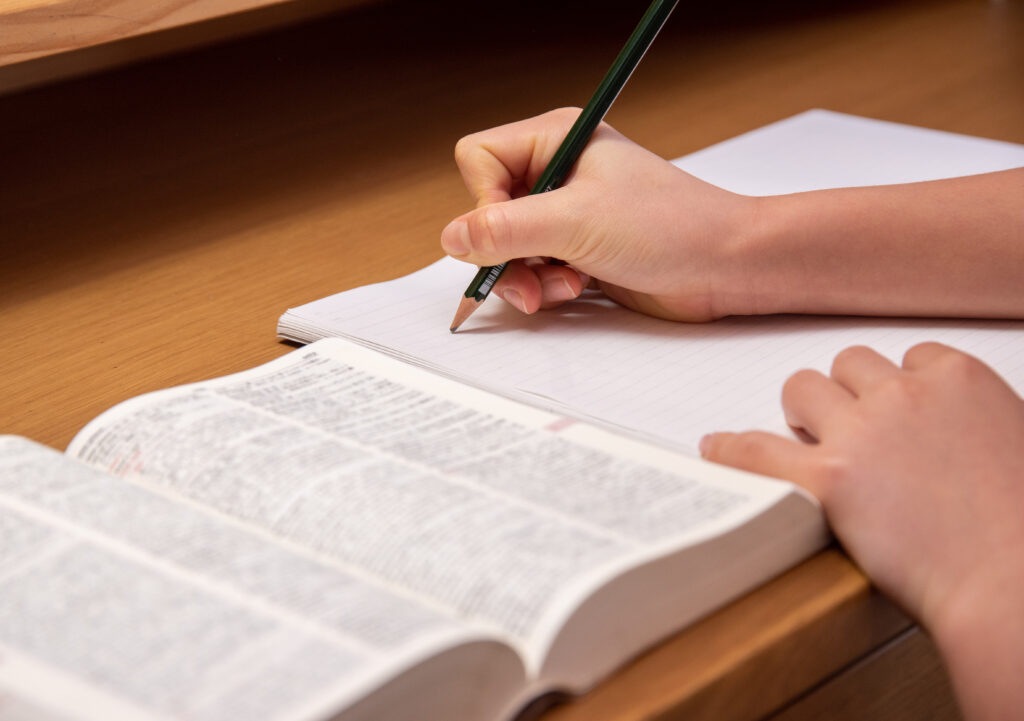
こちらでは大型二種免許資格を取得する手段ごとに、その難易度を解説します。
➀運転免許試験場で直接受験する
こちらの難易度は非常に高いのが現実です。
参考として平成27年度の合格率は約7.2%で平均受験回数は約14回になっています。
1回の受験で合格することはほぼ絶望的といってよいでしょう。
②公安委員会指定の教習所を受講する・③合宿免許
こちらの難易度は➀とは対照的に非常に低くなっています。
合格率に関しては約80~90%で、多くの方がほぼ1回の受験で合格しているのです。
近年は特に大型二種免許自体の合格率が上がってきています。
平成17年での合格率が約30.2%であったのに対して、10年後の平成27年では合格率が約51.8%と上昇しています。
その反面、受験者が平成17年のときは約6万人であったのに対して、平成27年では約2万5千人と半減しているのも特徴的です。
資格試験の難易度として受験者が減少し、合格率が上がっているということは、全体的に合格しやすくなったと言えます。
しかし、受験者数が減っているからこそ、バス運転手の人手不足が解消できずにいるとも言えるでしょう。
関連記事:バス運転手に転職するには?気になる勤務実態や民間・公営バス会社への応募方法を解説!
バス会社は研修と福利厚生が充実

現在では多くのバス会社が、資格支援制度を始めとする研修や福利厚生をこれまで以上に充実させています。
理由の1つは、人手不足による人材確保が急務だからです。
研修面では、先程述べた大型二種免許資格取得制度以外にも多くの資格支援制度を設けています。
資格支援制度を充実させる理由としては、自社におけるバス運転手を育てるだけでなく、運転手自体の運転技術の向上や、それに伴うバス会社自身の品質向上も図っているでしょう。
次に、福利厚生面では資格支援制度の他にも勤務時間及び休日設定の見直しや、有給休暇取得促進などが挙げられます。
また、女性専用の休憩所設置など、女性に配慮した福利厚生をおこなう企業も増加中です。
さらに給与面に関しても、賞与や資格手当などの各種手当も含めて、平均年収が約500万円前後になるなど、充分に生活ができる額が支給されています。
トラック会社より社員の面倒見が良い?
バス会社と運送会社は資格・免許こそ一種と二種に別れますが、どちらも大型車を取り扱う業界です。
またバス会社と運送会社は、どちらも近年における研修などの資格取得制度や、福利厚生の充実及び年収などの給与体系といった点に強化を図っています。
それは、どちらも人手不足による人材確保を気にしているからに他なりません。
よって、社員の面倒見に対して一概にバス会社と運送会社を比較することは難しいと言えます。
どちらも社員の保護には力を入れているところが多いので、あとは自分との相性が良い会社を選ぶと良いでしょう。
関連記事:バス運転手の給料はどれくらいもらえるの?職種や地域、年代別に分けて紹介!
バス運転手に必要な資格を取るメリットとデメリット

よくニュースなどでバス運転手は人手不足のために将来の展望が見えにくいといわれることがあります。
確かに人手不足の問題は事実ですが、決して将来性がないわけではありません。
外国人観光客の増加によって観光バスの需要が増えていますし、鉄道会社が夜行列車を削減している中、逆に夜行高速バスの需要は上がっています。
また給与面に関しても劇的に収入が増えることはありませんが、勤続年数が長くなるのと比例して年収も少しづつ上がっていきます。
安定を求める人にとっては相性のいい職場といえるでしょう。
さらに大型二種免許のように取得するのが大変な資格や免許は、一生使える価値あるものです。
これも長く働き続けることができる1つの要因といえるでしょう。
バス運転手のメリット
バス運転手のメリットには以下の6種類があります。
➀同じルートを走ることが多いので道順を覚えやすい
②基本1人勤務のため煩わしい人間関係によるストレスがない
③残業が基本的にはない
④乗客とのコミュニケーションを楽しむことができる
⑤就職または転職先が比較的多い
⑥子供たちの憧れの対象になれるかも?
この中で1つでも魅力に感じるものがある方は、バス運転手の仕事に向いているでしょう。
バス運転手のデメリット
続いて、バス運転手のデメリットには以下の4種類があります。
➀正月・GW・お盆休みがない
②シフトを組むため急に休むことができない
③運転中は電話をとることができない
④運転中は事故のリスクと隣り合わせ
このように、一般的な会社員の方と同じような祝日や休みが欲しい方には、バス運転手は向いていない可能性があります。
関連記事:もしもバスの運転手になったら!本当にきつい仕事なのか?
バス運転手に必要な資格に関してよくある質問

最後に、バス運転手の仕事に関してよくある質問に回答します。
運転中にトイレに行きたくなったら?
最後に番外編としてバス運転手のトイレ事情についてみていくことにします。
バス運転手は連続して運転をおこなえるのは4時間以内と法律で決められており、4時間を超えると30分以上の休憩をとる必要があります。言い換えるとバス運転手は原則4時間はトイレに行けなくなるともいえます。
そのためバス運転手は勤務前に以下のようなトイレ対策をおこなっています。
➀利尿作用のある食べ物を避ける
②利尿作用のある飲み物を避ける
➀の食べ物についてはワカメやひじき、大豆などが該当します。
②の飲み物についてはカフェインが入ったもの(コーヒー、お茶など)等が該当します。
トイレは休憩所や終点まで我慢するのが基本です。
どうしても我慢できなくなったときは、お客様に対してトイレに行く旨を説明した上で、公共施設などに停車した後、お客様の安全を確保した上でトイレに行くようにします。
関連記事:バス運転手を辞めたいと感じる理由とは?経験が役に立つ転職先も紹介
バス運転手に必要な資格についてのまとめ
バス運転手になるために必要な資格、大型自動車第二種運転免許は一生ものです。
長くドライバーとして働き続けるのであれば、多少の費用と手間がかかっても取得しておく方が良いでしょう。
バス会社の中には資格支援制度によって資格の取得費用を負担してくれるところもあるので、出費を抑えたい方にはオススメです。
弊社が運営するドライバー専門の求人サイト『ドライバーキャリア』では、そういった資格支援制度がある会社の求人情報だけを抽出することもできます。
バス運転手の求人情報に興味のある方は、以下よりお気軽にドライバーキャリアをご利用ください。
バス運転手の仕事をお探しの方へ
ドライバーキャリアは、運送・物流業界に特化した転職支援サービスです。
- 希望条件に合う求人のご紹介
- 履歴書など書類作成のサポート
- 企業との条件交渉/面接日程の調整
無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
求人を検索する(無料)