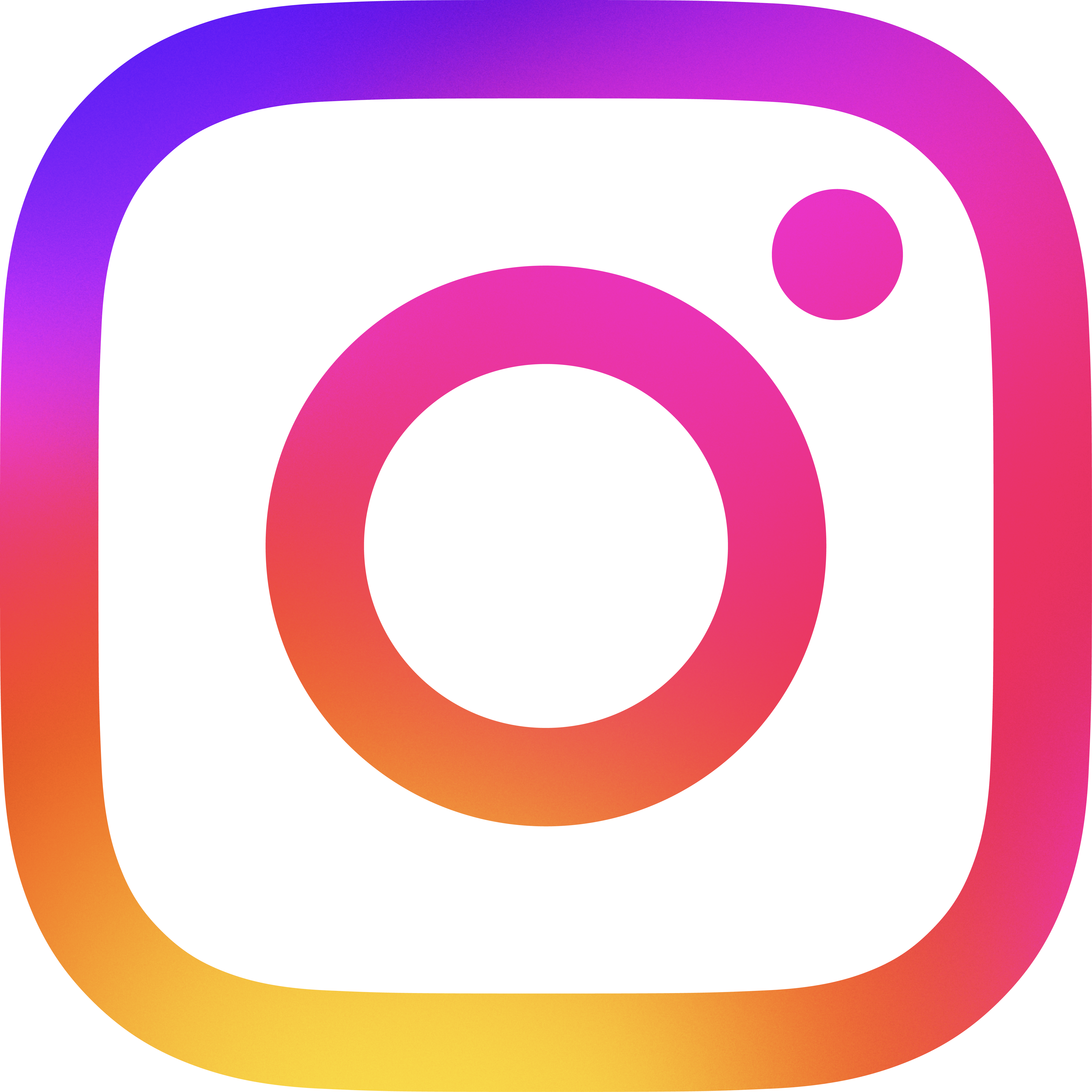中型免許には自動車用とバイク用とがあり、それぞれ取得費用が異なります。
また、取得方法や保有免許ごとにも取得費用が異なるため、それぞれ解説します。
中型免許の取得費用:自動車編

自動車の中型免許を教習所で取得する場合、合宿で取得する場合、一発試験で取得する場合の3つに分けて紹介します。
教習所で中型免許を取得する場合の費用
最も一般的と言えるのが、教習所で取得する方法です。教習所で中型免許を取得する際の費用は、保有免許によって異なります。
保有免許が普通免許:約17〜27万円
普通免許MTを保有している場合、学科の授業を1時限、実技教習を15時限受ける必要があります。
およそ4〜8週間程度かかり、費用としては17万円から24万円程度です。
一方、普通免許AT限定を所持している人は、学科の授業を1時限、実技教習を19時限受ける必要があります。
期間は変わらず4〜8週間ですが、費用はおよそ21万円から27万円ほどとなり、少し高くなります。
保有免許が8t限定中型免許:約10〜15万円
8t限定中型免許MTを既に持っている場合は、学科教習が不要となり、技能教習だけ5時限受ければ問題ありません。
4〜5日で完了し、約10万円の費用で取得できます。
また、8t限定中型免許AT限定の場合でも、同様に学科教習は必要なく技能教習は9時限です。
こちらも所要期間は同程度で、費用は約10万円から15万円程度となります。
保有免許が5t限定準中型免許:約15〜25万円
5t限定準中型免許MTを持つ場合、8t限定中型免許MTを持つ場合よりも教習内容が追加されます。
具体的には、不要だった学科教習が1時限増え、技能教習は6時限増えて11時限となります。
取得までにかかる期間は3〜8週間程度、費用は約15万円から20万円程度です。
一方、5t限定準中型免許AT限定を取得済みであれば、学科教習は同じ1時限ですが、技能教習の時限がさらに4時限増えて15時限になります。
期間はMTの場合と大きく変わりませんが、費用は約16万円から25万円程度かかります。
保有免許が準中型免許:約13〜19万円
準中型免許を保有している場合、学科教習は不要で技能教習のみ9時限を受ければ中型免許を取得できます。
取得期間は大体1〜3週間程度で、費用は約13万円から19万円程度となります。
合宿で中型免許を取得する場合の費用
続いて、合宿で中型免許を取得する場合の費用を紹介します。
保有免許が普通免許:約17〜30万円
普通免許MTを保有している場合、学科教習1時限と技能教習15時限を受ければ、約8〜10日で中型免許の取得が可能です。
費用はおよそ17万円から25万円程です。
一方、普通免許AT限定を持つ場合、学科は同じく1時限ですが技能教習は19時限が必要となり、10〜11日ほどの期間を要します。
費用は約18万円から30万円程度ですが、注意点として普通免許AT限定の所有者向けの合宿免許プランを提供している教習所は少ないのが現状です。
保有免許が8t限定中型免許:約7〜15万円
8t限定中型免許MTを保有している場合、追加の学科教習は必要なく、技能教習を5時限受講するだけで完了します。
所要期間は約3〜7日で、費用は大体7万円から15万円で済みます。
また、8t限定中型免許AT限定の免許を持っている場合も学科教習は必要ありません。
ただし、技能教習を9時限受けなければならないため、5〜6日程度の期間を要します。
取得費用は12万円から14万円程度です。
保有免許が5t限定準中型免許:約13〜25万円
5t限定準中型免許MTを持っている場合は、1時限の学科教習、11時限の技能教習を受講する必要があります。
所要期間は6〜8日ほどで、費用は13万円から25万円程度です。
一方、5t限定準中型免許AT限定を取得済みの人は、技能教習のみ4時限増えて15時限となるため、8〜10日の期間を要します。
費用は約16万円から25万円です。
保有免許が準中型免許:約13〜15万円
準中型免許を保有している場合、追加の学科教習は必要なく、技能教習9時限のみで中型免許の取得が可能です。
取得にかかる期間は約5〜6日程度で、費用は大体13万円から15万円となります。
一発試験で中型免許を取得する場合の費用
一発試験とは、教習所を経由せずに直接運転免許試験場で技能試験を受けることです。
合格するとその日に免許を取得できますが、技能試験の合格は難易度が高く多くの場合、何度も挑戦しなければ合格しない可能性があります。
受験費用は受験回数によって変わり、持っている免許の種類によっても異なります。
技能試験に合格した後、免許センターで必要な取得時講習を受ける必要があるので、講習費と免許交付のための費用は合わせて約22,000円程度です。
中型免許の取得費用:バイク編

バイクの中型免許(普通自動二輪車免許)の取得費用を紹介します。
教習所でバイクの中型免許を取得する場合の費用
教習所におけるバイクの中型免許の取得費用は、MT免許かAT限定免許かによって異なります。
普通自動二輪MT免許の取得:約10〜21万円
無免許の状態、または原付免許しか持っていない状態で普通自動二輪MT免許を取得するには、26時限の学科と19時限の技能が必要です。
この場合、取得までに1〜2ヶ月程度の時間がかかり、費用は約10万円から21万円程度となります。
一方、普通自動車免許を取得済みの人は、1時限の学科教習、17時限の技能教習をうける必要があります。
期間は同じく1〜2ヶ月ですが、費用は約9万円から13万円ほどで済むケースが多いです。
普通自動二輪AT限定免許の取得:約10〜20万円
普通自動二輪AT限定免許の取得では、必要な技能教習の時数がさらに減少します。
無免許の方や原付免許のみを持っている方の場合、同じく26時限の学科教習と、15時限の技能教習を受ける必要があります。
取得期間は1〜2ヶ月と変わらないものの、費用は約10万円から20万円であり、MT免許と比べて若干リーズナブルです。
一方、普通自動車免許を取得済みの人は、13時限の技能教習と、1時限の学科教習を受ける必要があります。
期間は同じく1〜2ヶ月ですが、費用はより低く、約8万円から12万円となります。
合宿でバイクの中型免許を取得する場合の費用
合宿における取得費用も、MTかATかによって変わります。
普通自動二輪MT免許を取得する場合:約11〜16万円
合宿免許は短期間での取得を目指しますので、普通自動二輪MTでも普通自動二輪AT限定でも、取得期間は10日前後です。
無免許の状態や原付免許のみ所持している場合、26時限の学科教習と19時限の技能教習を受けることが必要で、費用は約11万円から16万円が見込まれます。
既に普通自動車免許を所持している場合は、1時限の学科教習、17時限の技能教習を受講すればいいので、費用は約10万円から15万円程度となります。
普通自動二輪AT限定免許を取得する場合:約10〜20万円
AT限定免許を取得しようとする場合、無免許か原付免許のみの状態では学科を26時限受け、技能を15時限受ける必要があるため、費用は約10万円から15万円です。
既に普通自動車免許を取得済みの人は、学科を1時限、技能を13時限受ける必要があり、この場合の費用は約9万円から14万円となります。
一発試験でバイクの中型免許を取得する場合の費用
免許試験場での一発試験を選択した場合、合計費用は16,000円〜20,000円程度です。
内訳としては、免許証交付にかかる手数料が2,000円程度、試験車の使用料が1,500円程度、必須の講習費用が16,000円程度となります。
初見では教習所を通じて取得するよりもコストが低いように見えますが、一発試験で技能試験に合格するのは難易度が高いです。
合格するには通常3〜5回、平均して10回以上の受験が必要と言われており、そのため実際の費用は想定以上にかかると思っていいでしょう。
なお、料金は変更されることがあるため、正確な情報については最寄りの免許センターでご確認ください。
トラック・バイクの中型免許取得に利用できる給付金制度

中型自動車免許の費用は、給付金制度を活用することで負担を軽減できる場合があります。
そこで、ここでは2つの制度を紹介します。
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は働く人々のスキル向上やキャリア開発を支援し、雇用の促進と就職の安定を目指す雇用保険の給付プログラムです。
中型自動車免許の取得を含む一般教育訓練の受講費用に対して、20%(最大10万円)の給付が受けられます。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、企業が従業員の能力向上や教育プログラム導入をサポートするための財政支援を提供する制度で、中型自動車免許の取得にも適用されます。
受講料の45%が支給され、受講1時間あたりの上限は760円です。これにより、中型免許の取得費用を約半分に削減することが可能です。
この制度は特に運送業界での人材募集において、重要な役割を果たしています。
たとえば、中型免許を必要とする職種において、中型免許を持っていない応募者でも、企業がこの制度を活用することで免許の取得を金銭的に支援できるからです。
このような支援により、応募者は免許取得の経済的負担を軽減され、企業は必要な資格を持った従業員を育成できるという相互のメリットが生まれます。
中型免許を取るなら知っておくべき費用以外のこと

中型免許は普通免許や大型免許と違い、似たような名称の免許が複数存在します。
また、バイクの免許は中型以外にも複数存在し、乗りたい車両によって必要な免許が異なります。
そこで、こちらでは自動車における中型免許の種類と、バイクの免許の種類を紹介します。
免許の違い
中型免許、8t限定中型免許、5t限定準中型免許、準中型免許、それぞれの違いは以下の通りです。
中型免許
中型免許では、総重量が5t以上11t未満、最大積載量が3t以上6.5t未満の車両、または乗車定員が11人以上29人以下の車両を運転できます。
ただし、職業としてマイクロバスなどを運転する場合は、第二種中型免許が必要です。
8t限定中型免許
2007年の道路交通法改正以前に普通自動車免許を取得した人々は、その改正により自動的に「8t限定中型免許」を持つことになりました。
この免許では、総重量8t以下の車両を運転可能です。
5t限定準中型免許
2017年の道路交通法の再改正で、普通自動車免許で運転できる車両の規模がさらに変更されました。
この結果、2007年改正後から2017年改正前に免許を取得した人々は「5t限定準中型免許」の所持者となり、最大5tの車両の運転が可能となりました。
準中型免許
準中型免許は、2017年の道路交通法改正で新設された免許です。この免許では、総重量7.5t未満の車両を運転可能です。
このように、中型免許とそれに関連する限定免許は、運転できる車両の種類や規模に応じて異なります。
なお、限定免許所持者は限定解除試験を受けることで、中型免許や準中型免許への繰り上げが可能です。
試験に合格すれば、より大型の車両や特定の用途に合った車両を運転できるようになります。
道路交通法の改正に伴い、これらの免許の区分や条件は変化しているため、免許を取得する際は、最新の情報を確認することが重要です。
バイク免許の種類
バイクの免許には複数の種類があり、その中に「普通自動二輪車免許」いわゆる「バイクの中型免許」が含まれます。
排気量400cc未満の「中型バイク」を運転できることから、通称で「中型免許」と呼ばれているのです。中型免許以外のバイクの免許の種類は以下の通りです。
原動機付自転車免許(原付免許)
16歳から取得可能で、排気量50cc以下のバイクを運転できますが、2人乗りは禁止です。
小型限定普通自動二輪車免許
16歳から取得可能で、排気量125cc以下のバイクが運転でき、2人乗りも可能ですが、高速道路の使用は許可されていません。
マニュアル車(MT)とオートマ車(AT限定)の2種類があります。
大型自動二輪車免許
18歳以上から取得可能で、MTの場合は排気量無制限、AT限定の場合は650cc以下のバイクを運転できます。
2人乗りや高速道路走行が可能です。
中型免許の取得要件について

ここでは自動車とバイク、それぞれの中型免許の取得要件を紹介します。
自動車の場合
中型免許の取得要件は以下の通りです。
年齢と経験
満20歳以上で、普通自動車免許の取得から2年以上が経過している人が対象です。
二輪免許のみの保有者はこの条件に該当しません。
視力
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上の視力が求められます。
また、深視力誤差は20mm以内でなければなりません。
これは普通免許の取得時よりも厳しい条件です。
色覚
赤、青、黄の3色を正しく識別できる必要があります。
この条件は普通免許の取得時と変わりません。
聴力
日常会話が理解できる程度の聴力が求められます。
補聴器を使用していても構いませんが、不安な場合は事前に相談することをおすすめします。
運動能力
自動車を運転する上で支障がない運動能力が必要です。
これらの条件をクリアしていれば、中型自動車免許の取得が可能です。
バイクの場合
バイクの中型免許(普通自動二輪車免許)の取得要件は以下の通りです。
年齢
満16歳以上の方が取得できます。
16歳の誕生日の約1週間前から、教習に入校できる教習所もあります。
視力
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上の視力が求められますが、メガネやコンタクトレンズを使用してこの基準を満たすことができれば問題ありません。
片眼の視力が矯正しても0.3未満の場合は、左右150°以上の視野があるかどうかの検査が必要です。
色覚
赤、青、黄色を区別できることが必要で、信号の色を正確に識別できるかどうかが試されます。
聴力
日常会話が理解できるレベルの聴力が求められます。
具体的には、10メートル離れた場所から発せられる90デシベルの警報音を聞き取る聴力が必要です。
運動能力
バイクを運転する上で障害がないことが条件となります。
何らかの障害がある場合には、教習所に相談することをおすすめします。
中型免許を取得した先のキャリア

中型免許を取得すると、さまざまな職業でのチャンスが広がります。
中型免許は、トラックドライバーやルート配送、送迎サービス、引越し業など、多くのドライバー職で必要な免許だからです。
具体的には、地元や遠くまでのトラック配送、店舗間の商品配送、29人以下のマイクロバスでの送迎業務などが挙げられます。
特に、飲料メーカーなどでは中型車が多く使われるため、中型免許があれば多くの業務を担えるようになります。
引越し業界でも、中型トラックでの荷物運搬に中型免許は欠かせません。
また、第一種免許だけでなく、第二種免許を取得すれば人を有償で運ぶことも可能になり、新しいキャリアの道が開けるでしょう。
一方で、2024年にはトラックドライバーの労働時間に関する新規制が導入され、それが「2024年問題」として業界内で課題となっています。
この規制によりドライバー不足の加速が懸念されているので、中型免許を持っていれば、運送業界で重宝される存在になるでしょう。
中型免許の取得費用についてのまとめ

中型免許の取得費用は、保有する免許の種類や取得方法によって異なります。
一般的に、普通自動車免許を持っている場合は費用が少なく、教習所や合宿、一発試験の選択によっても変動します。
費用は10万円から25万円程度で、教育訓練給付金や助成金を活用することで、実質的な負担を減らすことも可能です。
中型免許を取得する際は、これらの費用や支援制度を事前に確認し、計画的に進めましょう。
ドライバーの仕事をお探しの方へ
ドライバーキャリアは、運送・物流業界に特化した転職支援サービスです。
- 希望条件に合う求人のご紹介
- 履歴書など書類作成のサポート
- 企業との条件交渉/面接日程の調整
無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
求人を検索する(無料)