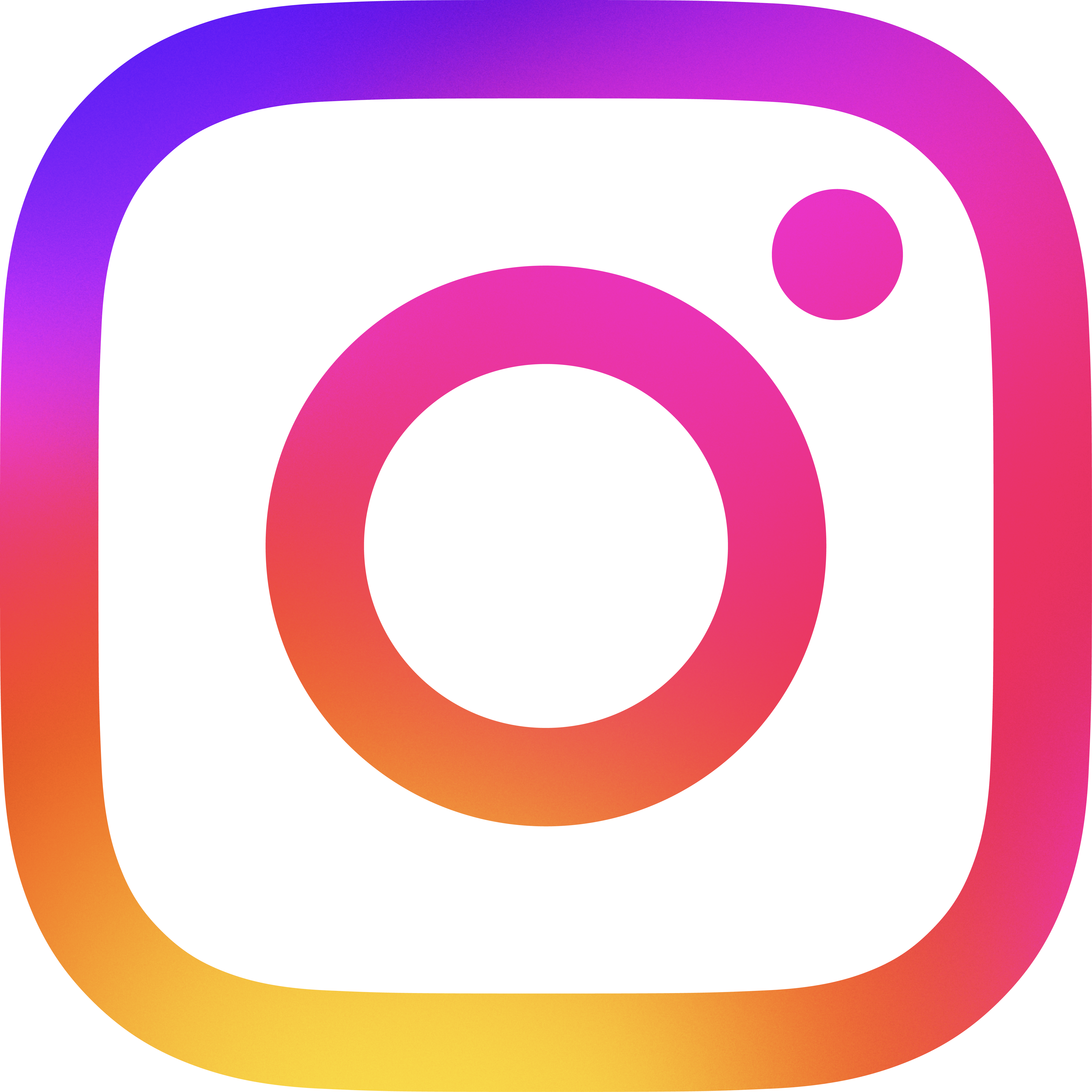運転免許を取得する際、多くの人が気になるのが費用です。
特に、準中型免許は普通免許と中型免許の中間に位置する資格であり、その取得費用がどの程度になるのかはあまり知られていません。
そこで本記事では、準中型免許の取得費用、取得するメリット、取得方法などについて解説します。
準中型免許の取得にかかる費用と期間

続いては、準中型免許の取得にかかる費用と期間について「教習所通学」「合宿免許」「一発試験」の3つに分けて解説します。
教習所に通学した場合
教習所通学の費用は、約35万円~とされています。期間は人にもよりますが、最短でも約3~4週間程度は必要です。
ただし、厳密にいうと取得費用は、所持している免許によって異なります。たとえば、東京都の拝島自動車教習所における準中型免許の取得費用は、それぞれ以下のようになっています。
| 保有免許 |
免許なし |
自動二輪免所持 |
普通車MT免所持 |
普通車AT免所持 |
大型特殊免所持 |
|
入所事務手数料 |
16,500円(税込) |
||||
|
入所金 |
121,000円(税込) |
||||
|
教本・写真代 |
4,400円(税込) |
2,420円(税込) |
770円(税込) |
770円(税込) |
2,420円(税込) |
|
学科教習料金 |
43,120円(税込) |
6,160円(税込) |
3,080円(税込) |
3,080円(税込) |
9,240円(税込) |
|
入所時合計 |
185,020円(税込) |
146,080円(税込) |
141,350円(税込) |
141,350円(税込) |
149,160円(税込) |
|
教習料計 |
213,620円(税込) |
202,950円(税込) |
74,250円(税込) |
94,050円(税込) |
163,350円(税込) |
|
費用合計 |
398,640円(税込) |
349,030円(税込) |
215,600円(税込) |
235,400円(税込) |
312,510円(税込) |
何の免許も所持していない場合の準中型免許の取得費用は398,640円(税込)であり、最高額となっています。
逆に、取得費用が最も安かったのは普通車MT免許を所持する場合で、215,600円(税込)でした。
教習所によって金額の違いはありますが、基本的にはどこの教習所でも所持している免許によって取得費用は変わります。
なお、教習所通学の場合は講習の受講に予約が必要です。繁忙期や時間帯によっては取りたい日時に予約が取れない場合もあります。
中には、追加料金を払えば優先的な予約枠を提供する教習所もありますが、その分費用はかさみます。
合宿免許の場合
合宿免許の費用は閑散期(4~7月中旬または10~1月)と繁忙期(7月下旬~9月、2~3月)で異なる場合がほとんどで、閑散期が約25万円~、繁忙期は約30万円~となります。
また、合宿免許は泊まり込みで集中的に受講するため、最短で約3週間で修了検定・卒業技能検定まで受講することができます。
一発試験の場合
一発試験の場合の受験費用は、受験料、試験車使用料、免許証交付料を合わせて8,650円、その後の取得時講習受講料が32,200円(普通免許を持っていない場合、所有者の場合は17,800円)となっています。
また、所要期間も教習所や合宿免許よりも圧倒的に短くなっています。
どの方法が一番安いのか
期間と費用だけを見ると一発試験が最もお得です。しかし、前述の通り一発試験はかなりハードルが高く、特に初心者の方にはおすすめできません。そこでおすすめしたいのが合宿免許です。
まずは費用面ですが、基本的には合宿免許の方が教習所通学よりもお得になる場合がほとんどです。
合宿免許は、前述の約25万円(約30万円)~に、教習料金や宿泊費用、往復の交通費など、すべての費用が含まれている場合がほとんどで、その他に費用はかかりません。
もちろん、既定の期間内に試験に合格できなかった場合には、追加の滞在費用と教習費用を払わなければなりませんが、教習所のカリキュラムをまじめにこなしていれば、試験に落ちることはほとんどありません。
また、期間も最短で約3週間で取得できるため、教習所通学よりも短期間で免許を取得できる可能性が高いです。
以上の理由から、最もお得に免許を取得できるのは、合宿免許であると言えます。
準中型免許に関して費用以外に知っておきたいこと

準中型免許取得の費用について説明する前に、まずは準中型免許がどのような免許であるかを説明します。
準中型免許は平成29年に導入された免許
準中型免許は平成29年より新たに導入された日本の運転免許の一種で、普通車に加えて最大総重量が7.5t未満、最大積載量が4.5t未満のトラックやバスを運転することができる資格を指します。
準中型免許は、運輸業やバス会社などで働く際のステップアップとして、または自身のビジネスで中型の車両を使用する際に取得する人が多い資格とされています。
準中型免許ができた理由
準中型免許のできた経緯には、大きく2つの理由が存在します。
トラックドライバーの不足
日本の経済が拡大する中で、物流産業も大きく成長してきました。その中心に位置するのが、「2tトラック」という車種です。
この「2tトラック」は、3t~4.5tの積載量を持つものが主流で、以前は中型免許がないと運転することができませんでした。
しかし、中型免許の取得には「20歳以上」という年齢制限や「普通免許を2年以上保持」という条件があったため、高卒1年目の若手社員が、入社後すぐに運転するのは難しい状況でした。
この「中型免許の取得条件」が、トラックドライバーの人手不足を引き起こす大きな要因となっていたのです。
この問題を解決するために新設された準中型免許は、18歳から取得できるようになり、普通免許の保有期間の要件もなくなりました。
これにより、物流業界に新たに入った人々も、準中型免許を迅速に取得し、配送業務に携わることが可能となりました。
このように、物流業界のニーズに合わせて、準中型免許は生まれたわけです。
交通事故の削減
普通免許の教習は、大半が乗用車を対象としています。ですが、2017年以前は、普通免許だけで総重量5t未満の車を運転することが許可されていました。
これにより、実際に教習を受けていないような大型の車も、合法的に運転することができてしまっていたのです。
総重量5tを超える車の事故発生率は、他の車種に比べて顕著に高かったため、この状況に多くの懸念が寄せられていました。
この問題に対応するため、交通事故を減少させる目的で、準中型免許が導入されたのです。そして、実際の準中型免許誕生後の交通事故死亡者人数は以下のように推移していきました。
| 年度 | 人数 |
| 2015年 | 4,117 |
| 2016年 | 3,904 |
| 2017年 | 3,694 |
| 2018年 | 3,532 |
| 2019年 | 3,215 |
| 2020年 | 2,839 |
| 2021年 | 2,636 |
| 2022年 | 2,610 |
出典:統計表|警察庁
2015年と2022年の数字を比較すると、約37%も減少しています。 準中型免許の誕生と交通事故死亡者の数の関係を直接結び付けることはできませんが、準中型免許が交通事故の減少に一定の効果をもたらしていると言っても過言ではないでしょう。
出典:準中型免許って? 免許制度改正についても紹介|東京車人武蔵境教習所
準中型免許で運転できる車の種類
各運転免許で運転できる車両の範囲は、下記の表のとおりです。
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
| 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人まで |
| 5t限定準中型免許 | 3.5t以上5t未満 | 2t以上3t未満 | 10人まで |
| 準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人まで |
| 8t限定準中型免許 | 3.5t以上8t未満 | 2t以上5t未満 | 10人まで |
| 中型免許 | 7.5t以上~11t未満 | 4.5t以上~6.5t未満 | 29人まで |
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
そのため、準中型免許で運転できる範囲は、車両総重量が3.5t以上7.5t未満、最大積載量が2t以上4.5t未満、乗車定員が10人までの車両となります。
なお、車両総重量、最大積載量、乗車定員は、運転免許証と、運転する自動車に車載されている自動車検査証に記載されています。
関連記事:準中型免許で乗れるトラックの種類・重量・定員等を解説
準中型免許を取得するメリット
続いて、準中型免許を取得するメリットについて紹介します。
運転できる車両が増える
準中型免許を取得するメリットの1つ目は、運転できる車両が増えることです。
準中型免許を取得すれば、普通免許だけでは運転できない大型のバンやトラックなど、7.5t未満の車両を運転することが可能となります。
これにより、仕事の幅や選択肢が増えるだけでなく、プライベートでの利用シーンも増えるため、より多くのシチュエーションでの運転を楽しむことができます。
職業の選択肢が増える
準中型免許を取得するメリットの2つ目は、職業の選択肢が増えることです。
特に、運輸業界や物流業界では、多くの企業が準中型トラックを使用しており、準中型免許を持っていることで、新たな雇用のチャンスが増加します。
また、一般的なオフィスワークだけでなく、運転を中心とした仕事を希望する方にとっては、準中型免許は大きなアドバンテージとなるでしょう。
さらに、準中型免許を取得することで、給与面での評価が上がる場合もあり、キャリアアップを目指す上でのステップとしても非常に有効です。
時間や費用を節約できる
準中型免許を取得するメリットの3つ目は、時間や費用を節約できることです。
中型免許と比較すると、準中型免許の取得に必要な教習時間は短縮されており、それに伴い教習料も比較的安価になっています。そのため、忙しい人にとっては、短期間で効率的に資格を取得することが可能です。
また、資格取得のための出費を抑えられるため、経済的な負担も軽減されます。
このように、準中型免許は時間とコストの面でのメリットが大きく、多くの人々にとって魅力的な選択肢となっているのです。
準中型免許を取得するには

ここでは準中型免許の取得条件や方法を紹介します。
準中型免許の取得条件
準中型免許を取得する条件として、身体能力に関しては以下のように規定されています。
| 年齢 | 18歳以上 |
| 視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ0.5以上 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができる |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下 |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる |
| 運動能力 | ①自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がない。 ②自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるもの。 |
出典:取得条件|那須自動車学校
なお、視力に関してはメガネ・コンタクトレンズを使用した矯正視力でも問題はありません。
また、道路交通法の改正により、2014年6月1日より仮免許申請時に「質問票」の提出が義務づけられました。
この質問票は、過去5年以内の罹患経歴など、免許取得者の健康状態を調査するものです。具体的な質問項目は、以下の通りです。
| 質問項目 |
| ①過去5年以内に、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。 |
| ②過去5年以内に、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。 |
| ③過去5年以内に、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある。 |
|
④過去1年以内に、次のいずれかの状態に該当したことがある。
|
| ⑤病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 |
虚偽の記載をして提出すると罰則が適用されます。
出典:質問票について|警察庁
関連記事:準中型免許の取得条件は?身体能力・病気・教習に関して解説
準中型免許の取得方法
準中型免許の取得方法には大きく分けて「教習所」「合宿」「一発試験」の3つがあります。
まず免許を保有していない人は、教習所に通ったあと、運転免許センターで試験に合格する方法が一般的です。なお、教習の期限に関しては下記の通り規定が存在します。
|
教習期限 |
教習開始日より9ヶ月 |
|
卒業検定期限 |
全教習終了日より3ヶ月 ※その期限内に万が一教習が終了しなかったり、検定に合格しなかった場合はそれまでの教習が無効になる。 |
|
仮免許証の有効期間 |
6ヶ月 |
ちなみに、普通免許を所持する方が教習所で準中型免許を取得する場合、普通免許をいつ取得したかによって履修内容が異なります。以下がその詳細です。
- 平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方
準中型免許が新設された平成29年3月12日以降に取得している場合、13時間の技能教習と1時間の学科教習の履修が必要です。
- 平成29年3月12日より前に普通免許を取得した方
準中型免許が新設される前に普通免許を取得した方は、運転可能な車両の範囲が既存の普通免許よりも広いです。とはいえ準中型免許よりは範囲が狭く、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」という文言が免許に記載されることになっています。
そのため、準中型免許の新設前に普通免許を取得した方は、「5トン限定解除」をおこなうことで、準中型自動車(5トン以上7.5トン未満)の運転が可能な免許へと更新されます。なお、限定解除は指定教習所か運転免許センターで手続きが可能です。
また、教習所での受講以外にも、合宿形式での免許取得も可能です。合宿免許は、教習所の宿泊設備で生活しながら、短期集中的に運転技術を習得する方法です。
コストパフォーマンスが良く、時間をかけずに取得したい人に選ばれることが多いです。
さらに、試験場での一発試験という選択肢もあります。これは、自分で学習してから、試験場に直接申し込み、筆記と実技の試験を受ける方法です。
合格すれば、教習所の料金を気にせず免許が取れますが、初心者には難易度が高いと感じられることが多いです。
合宿や教習所での学習者は、同じコースを何度も練習するため、技能試験には合格しやすいと言われています。しかし、一発試験では未知のコースでの運転が求められるため、他の方法と比べて難易度が高いのが現実です。
準中型免許の費用に関してよくある質問

ここからは、準中型免許の費用に関してよくある質問に回答します。
準中型免許の限定解除の費用は?
準中型免許の限定解除をするために必要な費用は、下記の通りです。
| 所持している免許 | 限定解除後に取得する免許 | 費用 |
| 準中型(5t)限定AT免許 | 準中型免許 | 約10万円 |
| 準中型(5t)限定MT免許 | 準中型免許 | 約7万円 |
マニュアル(MT)とオートマ(AT)によって、費用には3万円ほどの差が生じます。また、上記の金額に加えて、免許センターにて解除の申請をする際に1,450円の手数料が別途必要となります。
それなりに費用はかかるものの、普通自動車免許の取得に比べるとかなり安い金額であると言えます。
準中型免許を普通免許ありの人が一発試験で受かるのは難しいですか?
結論から言うと難しいです。特に技能試験が高いハードルとなっており、未知のコースでの運転能力を試されます。
教習所や合宿で学習すると、特定のコースを繰り返し練習することができるため、合格率は向上します。しかし、一発試験ではそのような事前の準備が難しく、合格の難易度が上がってしまうのです。
初めての免許取得でいきなり準中型免許はありですか?
普通免許を取得してから、後々準中型免許を取得するのではなく、いきなり準中型免許を取得することは可能です。
技能講習や技能試験の回数が減るため、段階的に取得するよりも費用を抑えられるというメリットもあります。
準中型免許の費用についてのまとめ
準中型免許の費用は、現在所持している免許の種類や、普通免許を取得した時期によって異なります。
仕事で準中型免許の取得が必要な方は、自分がどちらのケースに該当するのか確認の上、予算を立ててみてください。