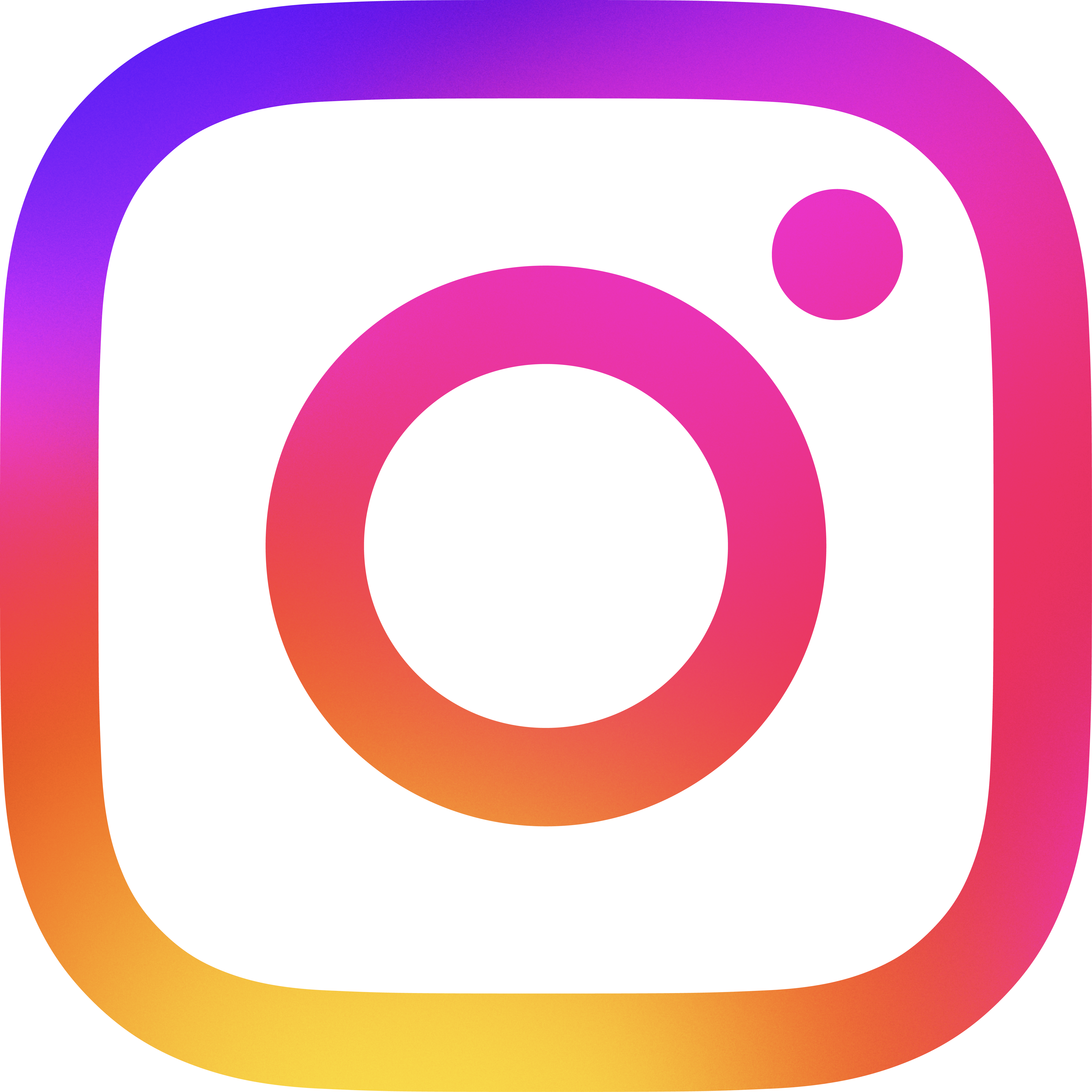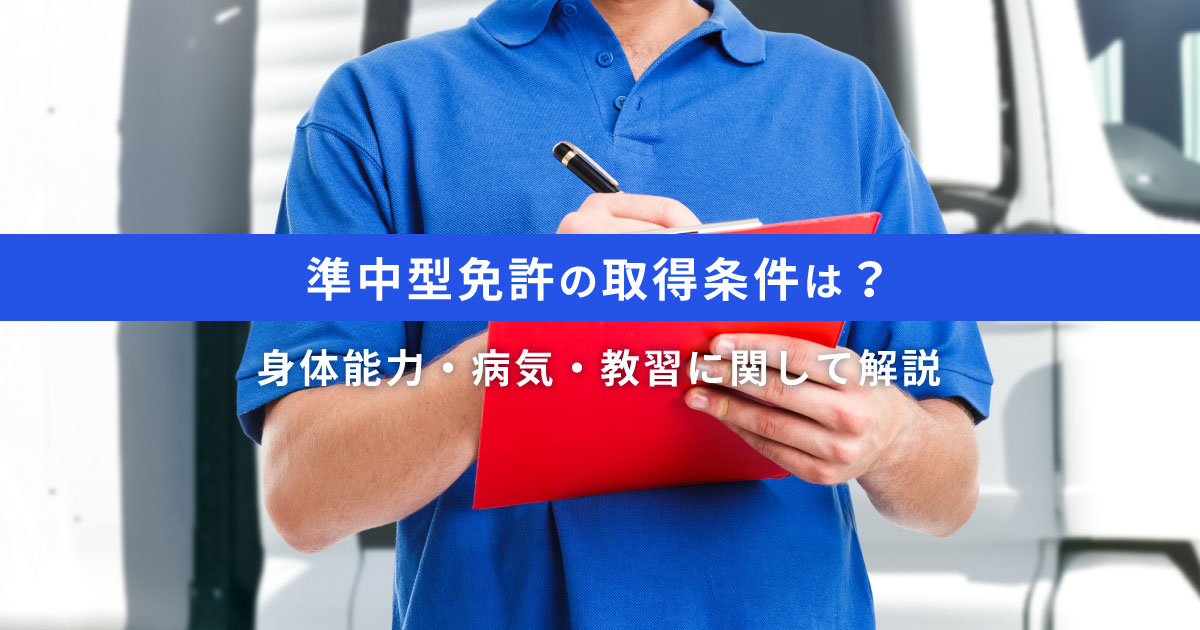
準中型免許は、多くの人々が日常生活や仕事で利用する車両を運転するための資格として注目されています。
しかし、この準中型免許を取得するためには、一定の条件や手続きが必要です。
そこで本記事では、準中型免許の取得条件や取得するメリット、取得する具体的な方法などについて詳しく解説します。
準中型免許とは:3.5t以上7.5t未満の車両を運転できる免許

準中型免許は日本の運転免許の種別の一つです。
この資格を有すると、車両総重量3.5~7.5t、最大積載量2~4.5t、乗車定員10人以下の車両の操縦が認められます。
これは、荷物を運ぶトラックや10人以下の乗客を収容するバスも対象となります。
しかし、11人以上の乗客を持つ大型バスや、さらに大きなトラックを運転する際には、中型免許あるいは大型免許の取得が求められます。
準中型免許の取得条件:新設で変わったこと

準中型免許が新設されたことで、運転できる車両の区分が大きく変更されました。
下記は準中型免許ができる前(法改正前)の区分です。そして、下記が準中型免許ができてから(法改正後)の区分です。
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 運転経歴 |
| 普通免許 | 5t未満 | 3t未満 | 10人まで | --- |
| 中型免許 | 5t以上11t未満 | 3t以上6.5t未満 | 11~29人まで | 普通免許等保有が通算2年以上 |
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 普通免許等保有が通算3年以上 |
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 運転経歴 |
| 普通免許 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人まで | --- |
| 準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | 10人まで | --- |
| 中型免許 | 7.5t以上~11t未満 | 4.5t以上~6.5t未満 | 29人まで | 普通免許等保有が通算2年以上 |
| 大型免許 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 普通免許等保有が通算3年以上 |
準中型免許を取得する条件として、身体能力に関しては以下のように規定されています。
| 年齢 | 18歳以上 |
| 視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ0.5以上 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができる |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下 |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる |
| 運動能力 |
①自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がない ②自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がある |
なお、視力に関してはメガネ・コンタクトレンズを使用した矯正視力でも問題はありません。
準中型免許の取得条件:病気に関して

道路交通法の改正により、2015年6月1日より仮免許申請時に「質問票」の提出が義務づけられました。
この質問票は、免許取得者の健康状態を調査するもので、下記5つの質問に回答する必要があります。
|
質問項目 |
|
①過去5年以内に、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある |
|
②過去5年以内に、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある |
|
③過去5年以内に、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある |
|
④過去1年以内に、次のいずれかの状態に該当したことがある 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続 けたことが3回以上ある 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある |
|
⑤病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている |
なお、この質問票に虚偽の記載をして提出すると、罰則が適用されます。
出典:警視庁「質問票について」
準中型免許の取得条件:教習に関して

準中型免許の取得においては、教習の期限に関しても下記の通り規定が存在します。
| 教習期限 | 教習開始日より9ヶ月 |
| 卒業検定期限 | 全教習終了日より3ヶ月 ※その期限内に万が一教習が終了しなかったり、検定に合格しなかった場合はそれまでの教習が無効 |
| 仮免許証の有効期間 | 6ヶ月 |
教習所に通学する場合は、上記の期限に関しても留意しなければなりません。
準中型免許を取得するメリット

準中型免許を取得することには、いくつかのメリットがあります。
まず、総重量が7.5トン以下の車両を運転することができるため、普通免許では運転できない大きめのトラックやバスを運転することが可能となります。
たとえば、コンビニへの配送に使われる「保冷車」などは、準中型免許で運転可能です。
これにより、ビジネスの幅が広がり、より多くの仕事のチャンスに繋がる可能性が高まります。
また、運転できる車両の種類が増えることで、プライベートでの利用の幅も広がります。
たとえば、大型のキャンピングカーや移動販売車など、特定の目的に合わせた車両の運転が可能です。
さらに、準中型免許は中型免許や大型免許へのステップとしても役立ち、将来的にさらに大きな車両を運転するための基盤を築くこともできます。
関連記事:7.5トントラックの運転に必要な免許は?準中型免許で乗れる?
準中型免許を取得する3つの方法

準中型免許を取得する方法は、大きく分けて3つ存在します。
合宿
1つ目は、合宿免許です。 この方法では、短期間で集中的に教習を受けることができるため、短期間で免許を取得したいと考える人に最適です。
合宿免許のプログラムは、宿泊施設と教習所がセットになっており、通常の教習所よりもコストパフォーマンスが良い場合が多いです。
通学
2つ目は、教習所通学です。 教習所に通ってから試験を受ける方法は、準中型免許を取得するための最も一般的なアプローチです。
教習所では専門の講師から直接指導を受けることができ、安全運転の基礎から実際の運転技術まで、しっかりとしたカリキュラムのもとで学ぶことができます。
模擬試験や実技教習など、試験に向けた十分な準備が行われるため、初心者でも安心して学べます。 また、教習所には最新の設備や教材が整っており、学習環境も整っています。
定期的に通うことで、継続的にスキルを磨くことができるのも大きなメリットです。
教習が終了した後は、所定の試験を受けて合格すれば、準中型免許の取得が完了します。
一発試験
3つ目は、運転免許試験場で一発試験を受ける方法です。 独学で必要な知識や技術を身につけた上で、直接試験場に申し込み、筆記試験と実技試験を受験するものです。
試験に合格さえすれば免許は取得できるため、教習所の受講料を節約できます。
しかし、独学での準備は、初学者にはハードルが高く感じられることがほとんどです。
このように、準中型免許を取得するには3つの選択肢があり、前提として、上記いずれの方法でも試験に受かりさえすれば、準中型免許を取得することは可能です。
ですが、免許試験の最難関は、試験場での「技能試験」です。
合宿免許や教習所通学の場合であれば、運転するのは教習所のコースのため、何度も運転して慣れている可能性が高く、合格はしやすいと言われています。
一方、一発試験の場合は、どうしても不慣れなコースでの運転となるため、合宿免許や教習所通学と比較すると不利であることは否めません。
したがって、準中型免許の取得方法については、このような点も考慮した上で検討する必要があるのです。
準中型免許の取得条件:必要な費用や期間

前述の3つの方法別に、準中型免許の取得にかかる費用や期間を紹介します。
| 期間 | 費用 | |
| 合宿免許 | 約2週間~ | 約25万円~ |
| 教習所通学 | 約3週間~ | 約30万円~ |
| 一発試験 | 1日~ | 約5万円~ |
費用を見れば、一発試験が圧倒的に低コストですが、先述の通り難易度は高く、あまり現実的な選択肢ではありません。
教習所通学は最短で約3週間で取得はできますが、教習の予約が取れない場合も多く、結局1ヶ月以上かかってしまうこともあります。
よって、一概には言えませんが、最短・最安で済ませたいのであれば、合宿免許がベストな選択肢と言えるでしょう。
関連記事:準中型免許で乗れるトラックの種類・重量・定員等を解説
準中型免許の取得条件に関してよくある質問

ここからは、準中型免許の取得条件に関してよくある質問に回答します。
旧普通免許は準中型自動車を運転できますか?
旧普通免許で運転できる車両の最大積載量は5t未満のため、5t未満の準中型自動車であれば旧普通免許でも運転できます。
しかし、5t以上の準中型自動車を運転する場合には、限定解除が必要です。
限定解除とは、特定の制限を持つ運転免許を、その制限を取り除くための手続きや試験を経て、一般的な免許にアップグレードすることを指します。
なお、限定解除をするには、教習や試験を受けるなど、所定の手続きが必要となります。
準中型免許はすぐに取得できますか?
準中型免許の取得には、必要な教習時間と試験に合格する必要があります。
教習所によっては、短期間での集中教習や合宿免許のプログラムを提供している場合もありますが、それでも一定の時間と努力が必要です。
また、筆記試験や実技試験に一発で合格するかどうかも、取得までの期間に影響します。
したがって「すぐに」と一概に言うことは難しいですが、計画的に進めれば短期間での取得も可能です。
準中型自動車免許は通学と合宿どちらがお得ですか?
準中型自動車免許の取得に関して、教習所通学と合宿のどちらがお得かは、個人の状況や目的によって異なるため一概には言えません。
合宿免許は、短期間で集中的に教習を受けることができ、宿泊費や食事費がパックになっているため、初めから終わりまでのコストが明確です。
しかし、規定の期間内に卒業試験に合格できなければ、期間延長となり、追加の料金が発生します。
一方、通学の場合は、自分のペースで教習を受けることができますが、通学の交通費や時間がかかることも考慮する必要があります。
また、地域や教習所によっても価格やサービスが異なるため、単純に比較することは難しく、自分で調べる必要があります。
ただし、これらの諸条件を無視して考えた場合、合宿免許の方が短期間かつ低コストで免許を取得できる可能性は高いため、合宿免許のほうがお得であると言えるでしょう。
関連記事:準中型免許の限定解除とは?5t未満しか運転できない理由
準中型免許の取得条件についてのまとめ

今回は、準中型免許の取得条件について詳しく解説しました。
準中型免許の取得を検討している方は、本記事を参考にして、ぜひ準中型免許の取得に挑戦してみてください。
ドライバーの仕事をお探しの方へ
ドライバーキャリアは、運送・物流業界に特化した転職支援サービスです。
- 希望条件に合う求人のご紹介
- 履歴書など書類作成のサポート
- 企業との条件交渉/面接日程の調整
無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
求人を検索する(無料)