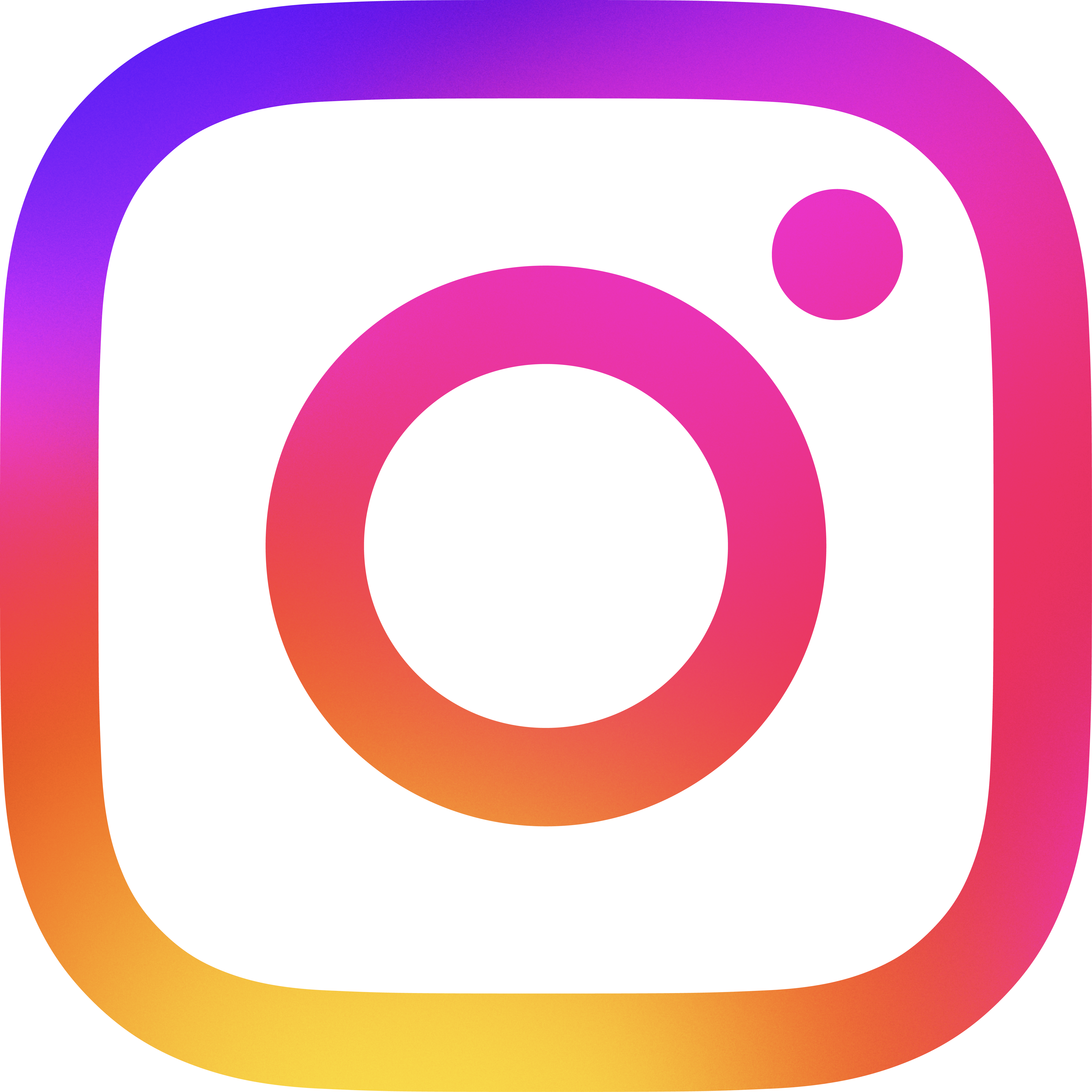建設業界において人手不足というのは長年続く深刻な問題です。それらを解消するために人材派遣を導入している企業が増えてきました。
しかし、派遣社員が一般社員と同じような作業をすることは禁止されています。派遣社員ができることは絞られているのです。禁止業務を行うと罰則が与えられるため、しっかりと理解を深めておくことが必須です。
この記事でわかることは以下の通りです。
・派遣禁止業務について
・建設業界における派遣禁止業務
・派遣禁止とならない業務
・施工管理における人材派遣の種類、メリット、デメリット
労働力の確保として派遣社員を採用することは有効な手立てです。そのため、今回の記事をしっかり読んで派遣社員の使い方を理解しましょう。
なぜ派遣禁止業務があるのか?

派遣とは
派遣とは、派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先企業で就業することをいいます。派遣契約の場合、派遣先の企業と派遣社員の間に指揮命令権があるため、業務中の指示は派遣際の担当者が直接行うこととなっています。
ただし、業務上のトラブルや問題が生じた場合は、派遣社員ではなく、派遣会社とやりとりを行うこととなります。
派遣禁止業務とは?
派遣禁止業務とは、1986年に施行された労働者派遣法内にある、労働者を派遣することができない業務を定めた業務を指します。
労働者派遣法で定められている禁止業務とは?
現在派遣禁止業務として指定されている業務は以下の5つです。
1.港湾運送業務:ふ頭における貨物の輸送・保管・荷役・荷捌きなど積卸しを主体とする業務。
2.建設業務:建築土木現場における業務。作業だけでなく準備も含む。
3.警備業務:企業や個人宅、公共施設や駐車場、行楽地などの施設において事故の発生を防ぐために警備する業務。他にも輸送中の現金や貴金属などの盗難を防ぐための警備などの業務も含む。
4.病院、診療所などでの医療関連業務:医師や看護師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、栄養士、救急救命士など医療施設において医療全般に関わる業務。
5.弁護士、社会保険労務士などの士業:弁護士や税理士、司法書士、行政書士、公認会計士、弁理士など士業。
派遣禁止されている理由は?
派遣を禁止している理由は、それぞれの業務によって異なります。例えば港湾運送業務はオンとオフのピークの差が激しく、需要が不安定であるという理由です。
警備業務は警備業法上で請負形態で業務を処理していることが求められており、派遣を認めてしまうと業務が適正に行われない恐れがあるからです。
医療関連業務は医師や看護師など専門職がチームを形成して医療を行っています。派遣元が労働者を決定している派遣を認めてしまうと適切な医療を提供できない恐れがでてしまうから禁止としています。
弁護士などの士業は資格者個人個人がそれぞれ業務委託を受けて行うため、指揮命令を受けることがありません。そのため、労働者派遣の対象から除外されています。
派遣禁止業務に従事させた場合どうなる?
派遣禁止業務に従事させると違反行為となり、労働者派遣法に基づいた罰則が与えられます。この罰則は4段階に分けられています。
- ⑴1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
- ⑵1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ⑶6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- ⑷30万円以下の罰金
今回の派遣禁止業務に労働者を派遣した場合は、⑵の罰則が与えられます。しかし、さらに届出を怠り、虚偽の陳述や報告を行った場合は⑶または⑷の罰則となります。
また、派遣先の企業と派遣元の企業に労働者派遣の停止命令が下されます。
施工管理の求人を検索する(無料)施工管理における派遣禁止業務の具体例

上記で紹介したように建築業務は派遣禁止業務と規定されています。それでは具体的にどのような仕事が禁止されているのか、詳しく見ていきましょう。
建築現場での資材の運搬、組立、家屋の解体
マンションや個人宅、商業施設など建設現場において建築資材の運搬や組立業務が禁止となっています。
工事現場での掘削や埋め立て作業
マンションや商業施設などの建築現場だけでなく、道路やトンネル、橋や駅などのインフラ工事を行う現場の作業も派遣禁止業務となります。土木工事において掘削や埋め立て作業などを行うことが禁止されています。
建築または土木工事でのコンクリート合成や建材の加工
建築または土木工事では現場でコンクリートを作成したり建材を加工したりすることがあります。しかし、それらを派遣社員が行うことは禁止されています。
壁や天井、床の塗装や補修、固定、撤去
建築作業の中で壁や天井、床の塗装および補修作業を行うことは禁止されています。小さな亀裂や穴をふさぐような作業であっても派遣社員は行ってはいけません。
建築または土木工事現場内での資材や機材の配送
派遣社員が建築または土木工事現場で資材や機材を運ぶことは禁止されています。しかし、これらは現場内での禁止行為であるため、工場や倉庫などの外から資材を搬入することは派遣社員でも認められています。
電飾版や看板などの設置・撤去
派遣社員が外壁などに電飾版や看板などを設置することも禁止とされています。
配線・配管工事、機器類の設置
マンションや家、商業施設などの配線工事や配管工事を派遣社員が行うことも禁止されています。なお、配線工事、配管工事に使用する資材や機器類を設置することも禁止されています。
現場の整理、掃除
細かいことですが、工事作業後の現場掃除や整理なども派遣社員が行うことは禁止されています。
イベント会場の大型テント・大型舞台の設置
コンサートやトークライブなどイベントが行われる際に設置される大型テントや舞台を設置工事を派遣社員が行うことは禁止されています。しかし、大型ではなく簡易テントやイス、大道具・小道具の設置であれば派遣社員でも認められています。
仮設住宅(プレハブなど)の組立
地震などの災害が起きた際や住宅の改修工事などで人が仮住まいするために必要なプレハブの工事を派遣社員が行うことは禁止されています。
専任の主任技術者および監理技術者
工事現場には専任の主任技術者や監理技術者を配置することを法律で定められています。それらは請負業者の社員でなければいけないため、派遣社員が専任の主任技術者、監理技術者を担当することは禁止されています。
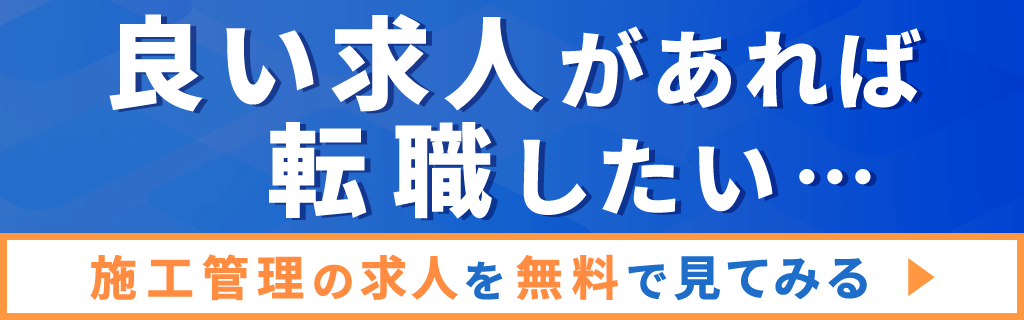
施工管理における派遣で禁止されていない業務の具体例
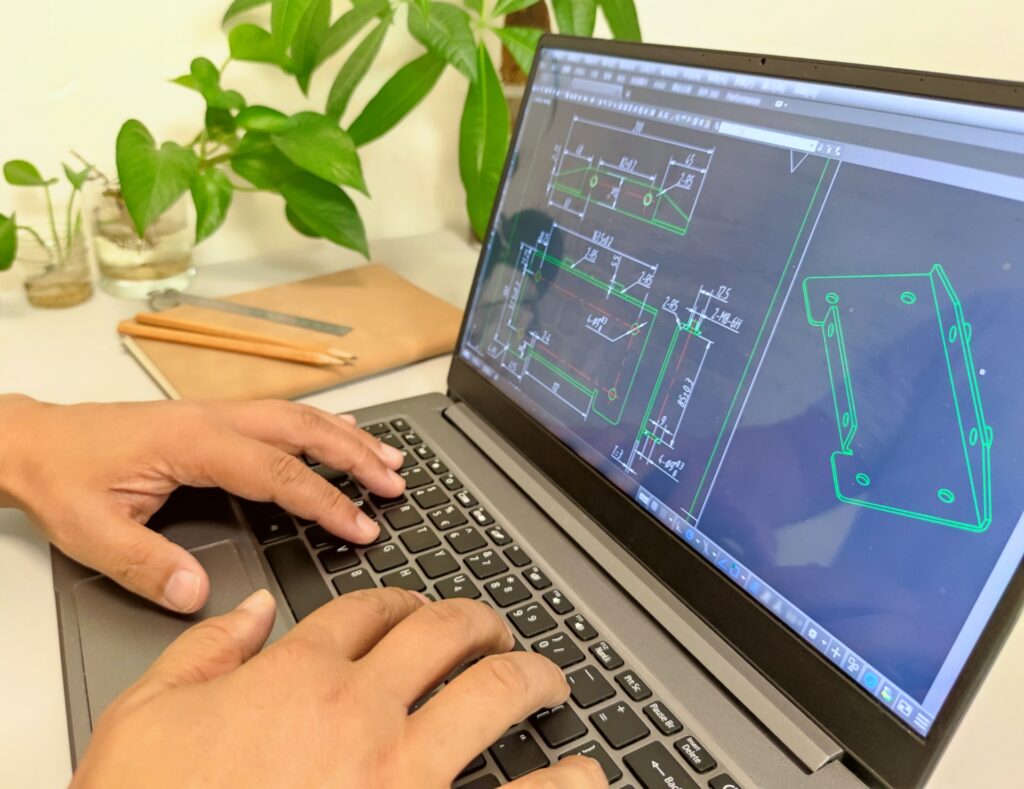
上記で紹介してきたように派遣社員は多くの建設業務を行うことを禁止されています。しかし、全てが禁止業務ではなく、いくつか派遣社員でも行うことができる仕事があります。
建設現場での事務作業
建設現場の事務所の中で事務作業を行うことは禁止されていません。建設現場で実際に作業することは禁止されていますが、事務所内での事務作業は建設業務に当てはまらないため禁止となりません。
また、CADオペレーターも派遣社員が行うことが可能です。建設現場での作業ではなく、事務所内での作業となるためです。
施工管理業務
施工管理業務とは、4大管理と呼ばれる「工程管理」「安全管理」「品質管理」「原価管理」です。
工程管理とは、工事のスケジュールを考え、工事中は現場の工事の進捗具合を確認して、職人に指示・管理を行う仕事です。職人の手配や重機のレンタル手配を行うことも工程管理に含まれます。
安全管理とは、工事を行う職人が安全に作業できるように安全点呼を行ったり、安全柵や命綱などに問題がないのか確認したり、現場周辺の近隣住民や通行人に危害を及ぼさないように安全を管理する仕事です。
品質管理とは、工事に使用する材料や構造が仕様書通りになっているのか、完成後は耐震強度などに問題ないかを確認する仕事です。
原価管理とは、予算内に工事が終了するように人件費や材料費、重機のレンタル料などの経費を管理する仕事です。
これらの施工管理は建設業務に当てはまらないため、派遣社員でも可能となっています。
施工管理における人材派遣の種類

人材派遣には契約の形態によって3種類のタイプがあります。それぞれに特徴、メリット、デメリットがあり、施工管理において人材派遣を導入する際はそれらを知っておくことが重要となります。
これらの人材派遣3種類をそれぞれ紹介していきましょう。
一般派遣契約
一般派遣契約とは、派遣会社から仕事を紹介されて、派遣先企業が見つかった期間だけ雇用契約が発生するものです。別名登録型派遣と呼ばれています。
派遣先での就業期間が終了すれば派遣会社との契約も終了するため、気軽に働くことができる契約方法となります。
一般派遣契約の場合のメリット
一般派遣契約の場合のメリットは、施工管理の初心者から熟練者まで幅広い人材を要望できます。施工管理の人材を求める企業の多くは派遣会社にあらかじめ募集する人材のスキルや経験年数を伝えています。
派遣会社はできる限りこの条件に当てはまるものを探し出して派遣するため、お互いにミスマッチすることがありません。派遣社員の給料や社会保険の計算は派遣会社が行うので面倒な手間がかからないのも良いところです。
一般派遣契約の場合のデメリット
しかし、デメリットもあります。大きなデメリットとしては一般派遣の場合、同じ企業では最大で3年までしか雇用することができません。
つまり、どれだけ素晴らしい人材が来たとしても3年後には契約終了となり、そうなれば大きな痛手となります。せっかく仕事を覚えもらっても、また一から新たな人材を育てないといけません。
また、一般派遣契約の場合はアルバイト感覚で登録する人材が多いため、経験豊富で高いスキルを持ったものが見つかりにくいという点があります。
もしいい人材が見つかれば正社員への雇用を打診してみるといいでしょう。
特定派遣契約
特定派遣契約とは派遣会社に正社員として無期限に雇用されて派遣先で働く契約方法です。別名常用型派遣とも呼ばれます。派遣先が決まっていない間でも給料が発生することがあります。正社員としての安定性や待遇の良さから人気の高い契約方法です。
特定派遣契約のメリット
特定派遣契約の場合は、比較的長期間派遣されることが一般的のため、そこで十分な経験とスキルを蓄えた労働者が多い傾向があります。そのため、施工管理として熟練者のものを派遣してもらいやすくなります。
特定派遣契約のデメリット
デメリットとしては、いくら優秀な派遣社員が来ても就業期間が終われば派遣会社に戻ることが規定されています。一般派遣契約のように正社員としての雇用切り替えができません。
紹介予定派遣契約
紹介予定派遣契約とは、最長6か月の派遣契約が終了したあとに派遣社員本人と派遣先企業の双方の合意があれば正社員または契約社員として直接雇用される契約方法です。
紹介予定派遣契約のメリット
派遣期間中は労使双方が使用期間のような見極めの期間となるため、その間に実力をしっかりとはかることができます。
また、6か月間を育成機関と考えると正社員を雇用し、育成するよりも人件費が安く済むといったメリットがあります。
紹介予定派遣契約は施工管理として長期間働いてもらうことが前提となります。一般的に正社員を雇用する際はインターネットやハローワークなどに求人広告を出したり、面接などの試験実施などの手間や経費がかかります。
しかし、紹介予定派遣契約であれば採用手続きは派遣会社が行ってくれるため、時間と費用のコスト削減となります。また、6か月間の適性の有無をはかる期間があるため、正社員採用後のミスマッチが起こりにくいメリットもあります。
紹介予定派遣契約のデメリット
デメリットとしては、この契約を行う施工管理の人材が少ないことです。この契約を行うというのは労働者側にそれなりの覚悟が必要です。
派遣会社を利用するものは気軽に働いてみたい、短期間の仕事を探しているといった方が多い傾向があります。そのため、一般派遣契約と比較すると応募人数が少ないことが特徴となります。
関連記事:施工管理の派遣会社ランキング!未経験な方やスキルアップしたい方、十分な研修を受けてから配属されたい方におすすめ!
施工管理における人材派遣についてのまとめ
施工管理の派遣はやっていい業務、禁止されている業務があったり、契約方法もさまざまあり複雑です。しかし、建設業界において施工管理の派遣社員導入は人材不足を解消するための有効な手段です。
今回の記事を参考に派遣禁止業務と禁止ではない業務をしっかり理解して、派遣会社から人材を募集してはどうでしょうか。
建設領域のお仕事をお探しの方へ
建職キャリアは、建設業界に特化した転職支援サービスです。
- 希望条件に合う求人のご紹介
- 履歴書など書類作成のサポート
- 企業との条件交渉/面接日程の調整
無料でご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
求人を検索する(無料)